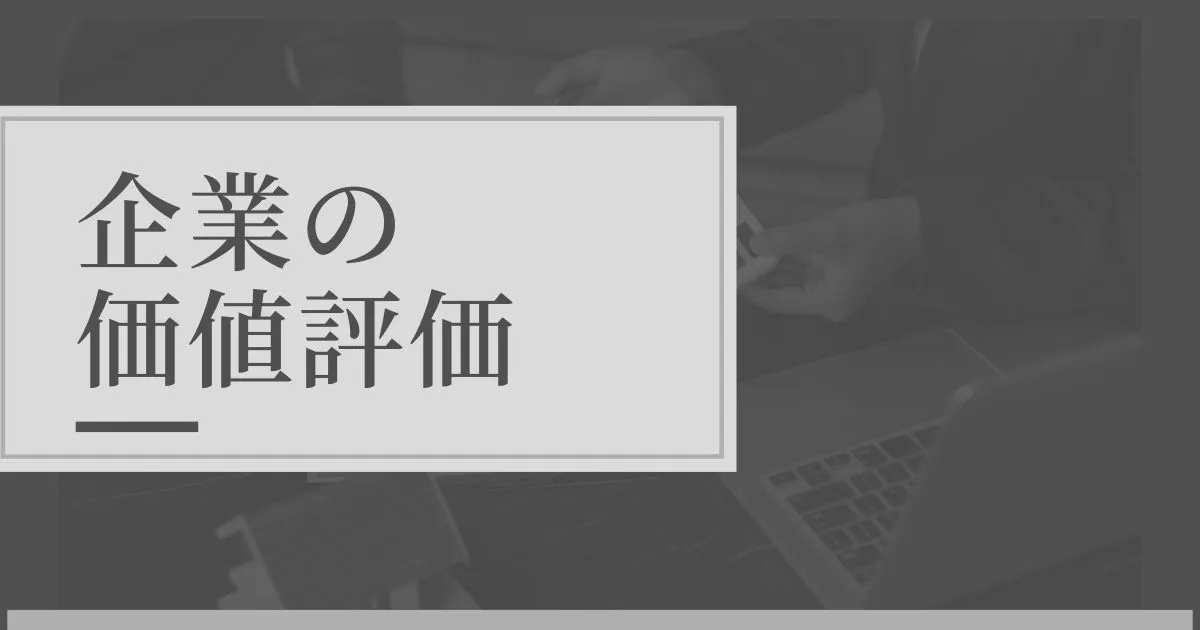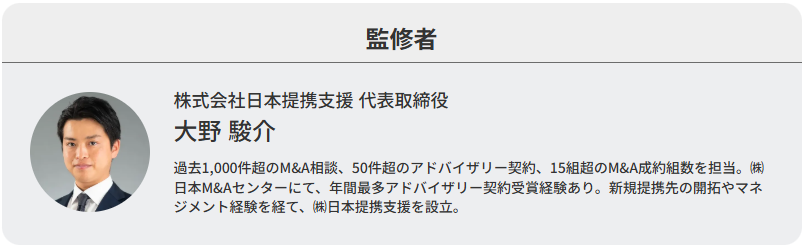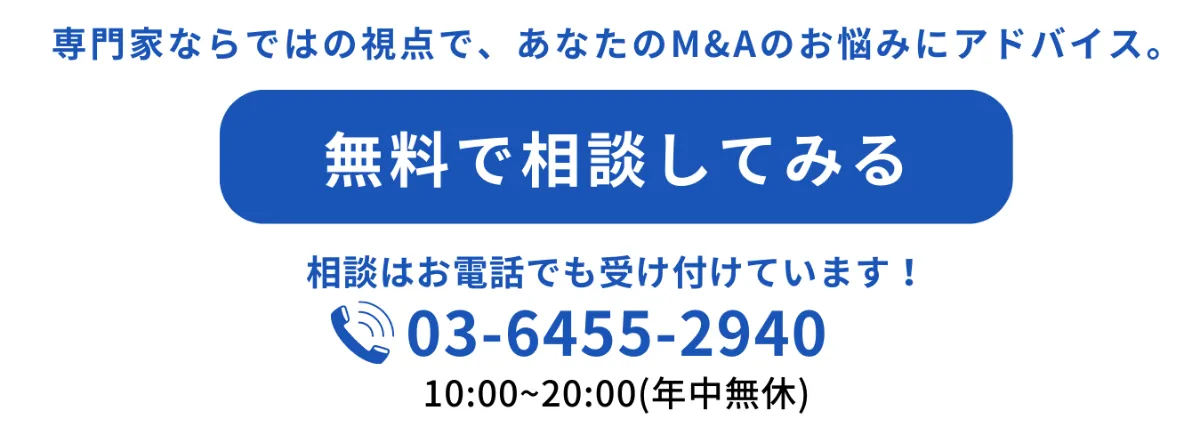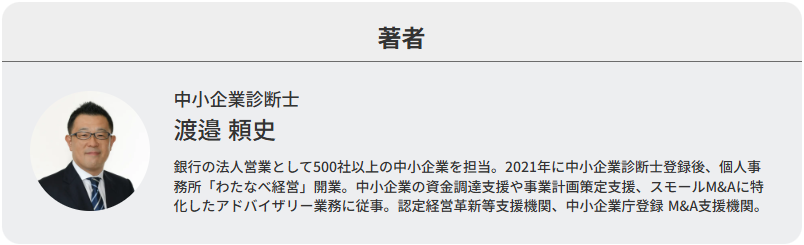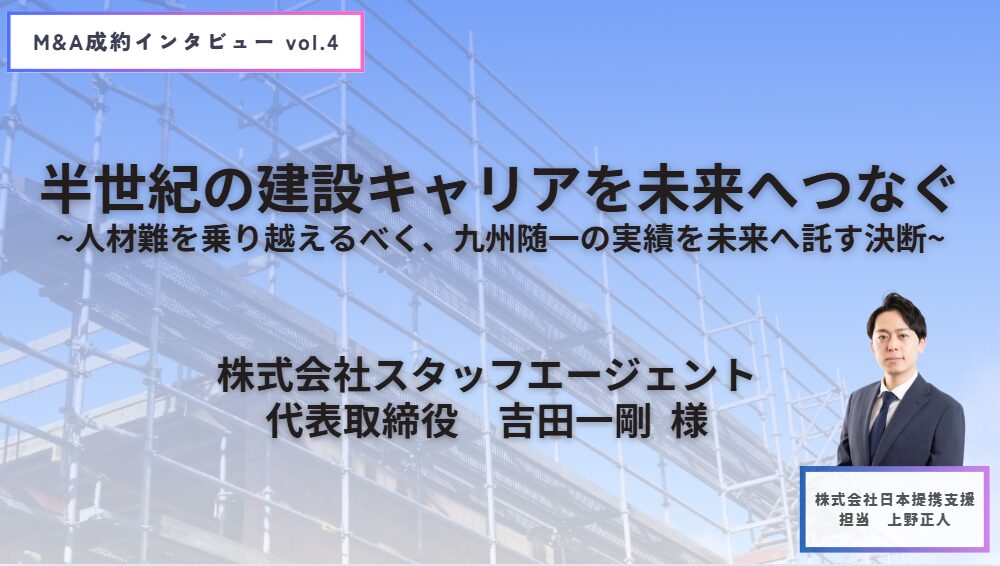M&Aにおけるバリュエーションとは企業価値評価であり、企業を売買する際の値付けを意味します。
上場企業のM&Aでは、株式市場で売買される株価を企業価値評価の目安としますが、非上場の中小企業において、市場株価は存在しません。
近年、中小企業によるM&A(スモールM&A)が注目されていますが、M&Aにおいて、バリュエーションは非常に重要なプロセスです。
M&Aに関心はあるが、バリュエーションをどのように進めたらよいかわからないという方に、今回はM&Aにおけるバリュエーションの意味や、評価手法などについてわかりやすく解説します。
M&Aバリュエーションの意義
M&Aにおけるバリュエーションの役割
バリュエーション(企業価値評価)とは、買収対象会社の事業やキャッシュフロー、資産負債を調査分析し、評価手法を用いて価値を算出することで、M&Aの際に非常に重要なプロセスです。
売り手および買い手にとって、M&A取引の最も重要な関心事は、買収価格(譲渡価格)です。売り手の関心は、自身の会社を少しでも高く売ることであり、買い手の関心は少しでも安く買うことです。
バリュエーションで合理的な企業価値を算出し、M&Aの際に価格交渉をする目安や、投資を実施するかどうかの判断基準で使われます。
バリュエーションの必要性
M&A取引において、論理的で説得力のある買収交渉を進めるにあたり、買収対象企業の適正かつ合理的な価格を設定することが非常に重要になります。
一般に、上場企業であれば、株式市場で取引される株価が存在するため、売り手または買い手にとって価格の目安とすることが出来ますが、非上場の中小企業にはそのような市場株価は存在しません。
企業価値評価にはいくつかの手法がありますので、評価方法や算定手法についてよく理解しておくことは、売り手または買い手いずれにおいても重要となります。
バリュエーションと取引価格の関係
M&Aにおけるバリュエーションと取引価格は密接な関係がありますが、必ずしも一致するわけではありません。
適切なバリュエーションが行われた場合、買収企業はその評価を基に合理的な取引価格を提示し、買収交渉において出発点となることがありますが、取引価格はバリュエーション以外の要素によっても影響を受けることがあります。
例えば、買収の戦略的な意図や市場環境、競合他社の存在、交渉力などが価格に影響を及ぼすことがあります。
また、企業価値評価にはいくつかの手法があり、唯一絶対的な方法というものはありませんので、売り手の希望価格と買い手の企業評価が大きく乖離することも珍しくありません。
バリュエーション手法の概観
バリュエーションの評価方法
バリュエーションの評価方法は以下のように分類されます。
-
マーケットアプローチ(市場基準方式)
-
インカムアプローチ(収益基準方式)
-
コストアプローチ(原価基準方式)
-
マーケットアプローチ(市場基準方式)
株式市場における取引価格や類似事例を参考に、株価を評価し、株式および事業の価値を算定する手法です。
主な算定方法は、類似会社比較法(倍率法)や類似取引比較法(買収事例)などがあります。
-
インカムアプローチ(収益基準方式)
評価対象企業の収益面に着目して、将来獲得する収益またはキャッシュフローを現在価値に割り引くことにより、評価額を算定する方法です。
主な算定方法は、DCF法、収益還元法などがあります。
-
コストアプローチ(原価基準方式)
資産項目と負債項目を個別に検討し、時価にて評価し、その差額である純資産を株主価値として評価する方法です。
主な算定方法は、時価純資産法、時価純資産プラスのれん(年買法、年倍法)などがあります。
類似会社比較法(倍率法)
類似会社比較法とは、評価対象会社と類似する会社(同業他社)を公開会社から選定し、財務データから、売上高、利益、各種の財務指標(利益倍率や資産倍率など)を算定し、評価対象会社へそれを適用して、株主価値、企業価値などを算定する方法です。
実務で多く使われるPER法は、1株当たり純資産の指標で、上場会社などの業界平均PER(株価収益率)を用い、評価対象会社の税引き後利益から株主価値を算定します。
DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)
DCF法は、対象企業や資産が将来生み出す収益(フリー・キャッシュフロー)を予測し、将来キャッシュフローについて、割引率を用い現在価値に割り引いて事業価値を算出し、非事業用資産を考慮した企業価値から他人資本である有利子負債を控除して、株主価値を算出する方法です。
合理的・論理的な計算方法であり、M&A実務において、広く利用されている方法です。
時価純資産法
資産の評価
具体的には、資産項目には不動産、有価証券、売掛金、棚卸資産、知的財産などが含まれます。
それぞれの価値を決定するために、資産価値、回収可能性、換金性、再調達原価などを考慮します。
負債の評価
一方、負債については、帳簿価格が支払額であり時価と認識されます。
また、帳簿に記載されていないオフバランス債務の存在も確認することが重要です。
その存在が確認できた場合、未計上であれば追加で計上します。
時価純資産プラスのれん(年買法、年倍法)
年買法は、中小企業M&A取引において一般に多く用いられる評価方法です。この方法では、時価純資産法をベースに、のれん相当額を実質利益の評価倍率で算定し、その合計が評価額となります。
年買法の利点
DCF法では将来キャッシュフローの予測など不確定要素が多く、また計算式が複雑であるため敬遠されがちです。
それに対して、年買法では決算書を基に簡易で素早く計算できます。売り手と買い手が計算方法を共有できるため、価格合意形成に多く用いられます。
年買法の計算方法
具体的な計算方法は以下の通りです。
企業評価額=時価純資産額+営業権(のれん)
営業権(のれん)=実態収益力×評価倍率(1~3倍)
評価倍率の決定
評価倍率は対象会社の業界、業種、事業基盤などにより評価されます。一般に3倍程度とされ、高いもので4~5倍、それ以上に評価されることもあります。
成長性が見込める業界(例えばIT業界)や、買い手候補が多数存在する業種(例えば運送業界)は、高い評価倍率を得やすいです。
さらに、ブランド力や強固な顧客基盤、特許などを持つ会社も高い評価倍率を獲得できます。
各手法の長所、短所と選択のポイント
バリュエーションの際にどの手法を採用するかは、売り手および買い手の立場や意向、それぞれの状況に応じ、各手法の長所や短所を比較検討し、採用することが重要です。
-
類似会社比較法(倍率法)
長所:公開情報やデータベースから比較的情報の入手が容易であり、素早く評価できる。株式市場に基づく、市場の現実性を反映した評価であり、一定程度の合理性がある。
短所:類似する公開企業の選定が困難な場合があり、選定に際し恣意性が入る可能性がある。評価対象企業の独自の特性や競争優位性を反映しきれない場合がある。
-
DCF法
長所:論理的な計算方法で、企業の経済的パフォーマンスに基づいた具体的な金額で評価することができる。
短所:キャッシュフローなど必要な情報を入手するのが困難な場合があり、将来のキャッシュフローの予測は不確実性を伴い、恣意性が入る可能性がある。また、他の評価方法に比べてプロセスが複雑であり、企業の非財務要素(ブランド価値、顧客基盤、知的財産など)を評価しきれない場合がある。
-
時価純資産法
長所:決算書などに基づき、企業の実際の資産の時価を評価に反映させるため、企業の実態に基づいた評価を行うことができる。また、会社清算価値(評価下限)を把握することができる。
短所:将来利益や無形資産の価値(ブランド価値、知的財産など)が反映されていない。
-
時価純資産プラスのれん
長所:企業の実態に基づいた評価に加え、無形資産である営業権(のれん)の評価が可能である。また、比較的簡易に価値を評価でき、わかりやすい。
短所:営業権(のれん)の評価につき、恣意性が入りやすく、論理的ではないため、客観的な基準の確立や評価の一貫性が求められる。
DCF法でバリュエーションを行う際のポイント
将来予想キャッシュフローの推定方法
将来のキャッシュフローを推定するには、企業の過去の財務情報や業績データ(収益性、成長率、キャッシュフローの変動パターンなど)、市場のトレンドや予測(産業・業界の成長率、市場シェアの変化、顧客ニーズの動向など)、マクロ経済要因(経済環境、金利・為替、税制など)を考慮しながら予測を行います。
その他、同業他社の業績やキャッシュフローのデータを参考にして、複数のシナリオや予測(楽観的シナリオ、保守的シナリオ、悲観的シナリオなど)を作成して検証することも有効になります。
参考:黒字倒産を防ぐファクタリング活用!資金繰りを安定させる戦略やキャッシュフローについて解説|ファクログ
割引率の設定
割引率は投資家が期待する収益率であり、将来のキャッシュフローや収益を現在価値に変換する際の利子率やリターン率と解釈できます。
割引率の意義
この割引率は時間的価値とリスク負担に対する報酬を示しています。
具体的には、金銭の価値が時間と共に減少するという経済の法則(時間的価値)と、投資に伴うリスクへの対価を示します。
割引率の決定法
DCF法では割引率として、加重平均資本コスト(WACC)が使われます。
WACCは、企業が複数の資本(株式や債券、有利子負債など)を使って事業を運営している際、それぞれの資本の調達コストを資本構成によって加重平均したものを指します。
WACCの計算方法
WACCの計算式は以下の通りです。
WACC = 負債コスト×(1-実効税率)×負債比率 + 株主資本コスト×株主資本比率
ここで、負債比率と株主資本比率は企業全体の資本に対する負債と株主資本の割合を示しています。
成長率の見積もり
成長率は、DCF法における大切な要素で、将来のキャッシュフローの見込み成長率によって企業の評価が大きく変動します。
定常成長率
よく使われる成長率の種類として定常成長率があります。定常成長率とは、企業が一定の成長率で継続的に成長するという前提で設定される長期的な成長率です。この値は通常、企業の過去の成長率や業界全体の成長率などを参照して推定されます。
一時的な成長率
一方で、企業が新たな市場への参入や大規模な投資を計画している場合、一定期間限定の高い成長率を考慮することもあります。新たな市場への参入や大規模な投資は、一時的に収益性を大きく向上させる可能性があるからです。
減退する成長率
業界や企業の特性により、成長率が徐々に下降すると見込むこともあります。これは、市場の飽和や競争の激化により成長が鈍化すると予測される場合に考慮されます。
バリュエーション結果の解釈とエラーの対処法
バリュエーション結果の解釈方法
バリュエーション結果の解釈は、企業や資産の評価を理解し、意思決定をするために重要です。
バリュエーション結果の解釈に関するポイントは、評価額の理解(根拠となる評価手法やデータ、仮定、将来の変化を考慮する)、比較と相対評価(同業他社や業界平均との比較)、リスクの考慮(リスクの度合いを適切に評価して、リスクとリターンのトレードオフを考慮)などがあります。
バリュエーションエラーの一般的な要因
バリュエーションにおいては、予測や仮定に基づく評価が行われるため、エラーが発生する可能性があります。
バリュエーションエラーの一般的な要因は、以下のとおりです。
データの品質と信頼性
バリュエーションに使用されるデータの品質や信頼性には注意か必要です。誤ったデータや古い情報を使用することで、評価結果に誤りが生じる可能性があります。
予測の不確実性
バリュエーションは将来の予測に基づいて行われますが、予測は不確実性を伴うものです。予測の誤差や変数の予測が外れることにより、評価結果にエラーが生じる可能性があります。
評価手法と割引率の誤り
バリュエーションでは複数の評価手法がありますので、採用する評価手法によって異なる評価となります。また、割引率の設定に誤りがあると、バリュエーション結果に影響を与えます。
適正なバリュエーションを得るための注意点
適正なバリュエーションを得るための注意点は、以下のとおりです。
・データの収集方法やソースの選定、データの検証プロセスに注意を払う
・感度分析やシナリオ分析を行い、不確実性を考慮する
・評価手法の慎重な検証、数値計算の正確性の確保
バリュエーションにおける専門家の役割
専門家によるバリュエーションのメリット
バリュエーションは複雑なプロセスであり、専門的な知識と経験が必要です。例えばバリュエーション結果の解釈では、複雑なプロセスになりますので専門的な知識や経験が求められる場合もありますので、専門家やアドバイザーの助言を活用することで、より適切な意思決定を行うことができます。
また、専門的なツールやデータベースを必要とすることも多く、例えば将来キャッシュフローを推定する際には、専門家やアナリストの意見、市場調査データ、業界レポートなどを参考にすることで、客観的かつ蓋然性の高い検証を行うことができます。
専門家の選び方
バリュエーションの専門知識と経験は、適切な専門家を選ぶ上で最も重要な要素です。評価手法やモデリング技術に精通していることや、業界知識が豊富であることが望ましいです。
また、専門家とのコミュニケーションや対応力も重要です。専門家の経歴や実績を確認し、専門家の信頼性や専門性を評価しましょう。
M&Aでお困りなら日本提携支援に相談
M&Aにおけるバリュエーションについて解説してきました。
正確なバリュエーションを行うには、非常に専門的な知識と豊富な経験を必要とします。
日本提携支援には豊富な実績、経験を有する専門家が多数在籍していますので、ご要望に合わせて、どのような専門家に依頼すべきかについてのアドバイスが可能です。
当社では相談者の方から手数料をいただいておりませんので、費用面でも安心してご相談いただけます。
M&Aにおけるバリュエーションをしっかりと成功させるために、是非我々日本提携支援にご相談ください。