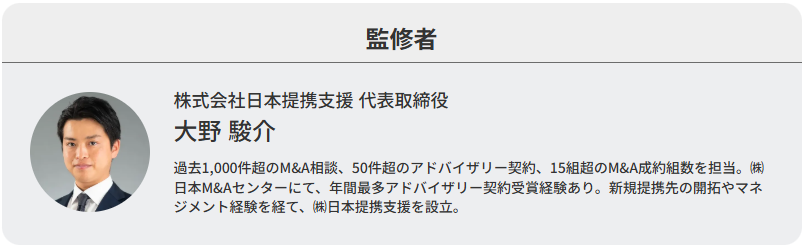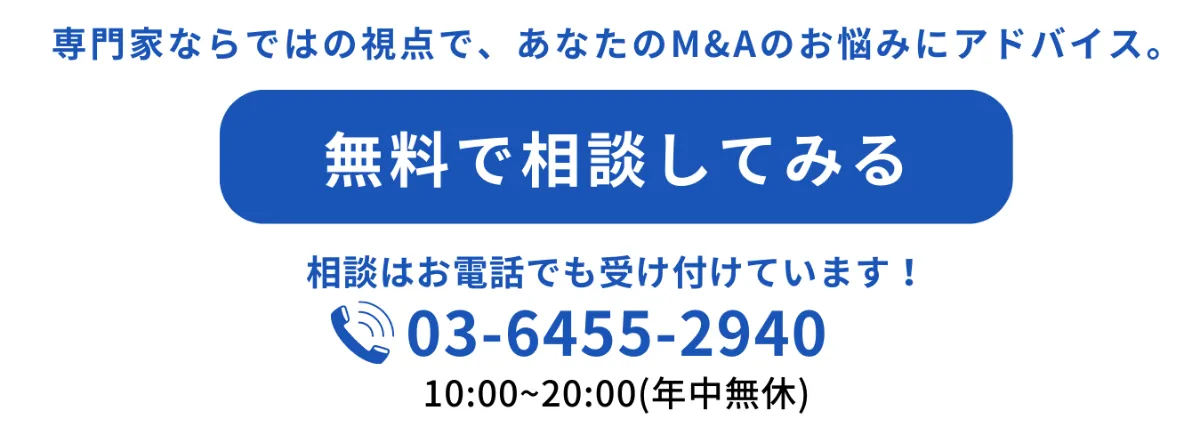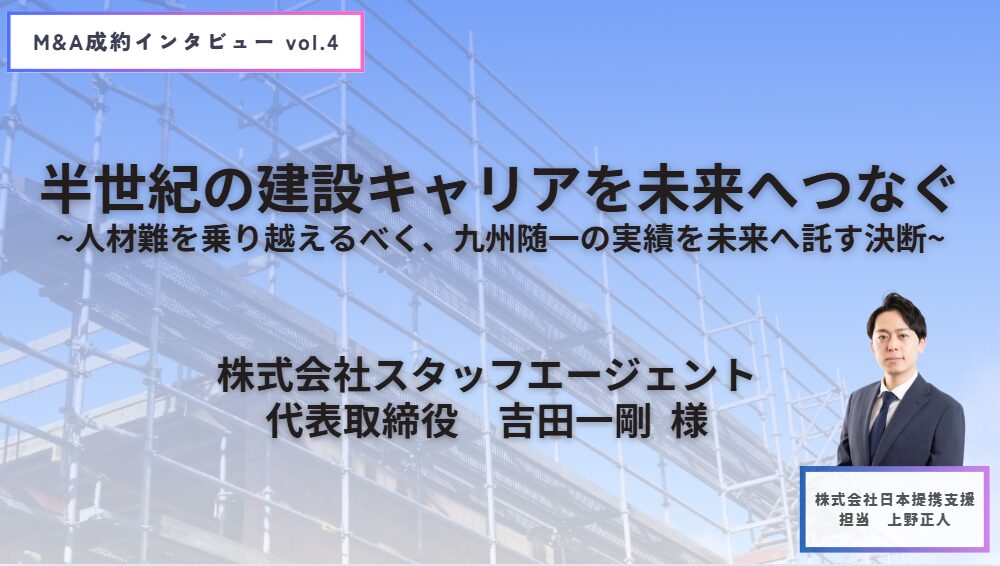中小企業庁中小M&Aガイドラインによると、我が国では2025年までに約245万人の中小企業経営者が平均引退年齢である70歳を超え、その内約半数が後継者未定と見込まれています。
このような状況下、近年中小企業ではM&Aを含む事業承継を検討する経営者が増加していますが、以下の事情によりなかなか検討が進まないケースも多く見られます。
-
日常業務で手いっぱいのため余力がない
-
どこからどのように手を付けたらよいかわからない
-
家族内の問題でもあるので気軽に他者に相談できない
M&Aを含む事業承継において検討すべき項目は多岐にわたり、高度な専門知識を必要とする場面も発生します。
自社人材だけでこのような課題に対処することが困難な中小企業にとって、専門家の活用が有効な対策となります。
本記事では、事業承継の専門家にはどのような機関があるのか、また依頼にあたってどのような点に留意すべきか等、事業承継に関する専門家活用のノウハウについて解説していきます。
事業承継専門家の役割と選び方
専門家の種類とそれぞれの役割
事業承継に関与する代表的な専門家とその役割は以下のとおりです。
|
専門家 |
主な役割 |
|
税理士 |
税務関連の助言、提案 |
|
弁護士 |
M&Aにおける法的アドバイス |
|
ファイナンシャル |
経営者個人の資産運用支援やマネープランの立案 |
|
M&Aアドバイザー |
譲渡候補企業の選定とマッチング |
|
中小企業診断士 |
会社が持つ強みの磨き上げ、企業価値向上への助言 |
|
司法書士 |
会社法に関連する法的手続き |
|
行政書士 |
許認可等の行政手続き |
|
金融機関 |
事前相談対応 |
|
中小企業基盤整備機構 |
事業承継・引継ぎ支援センターによるワンストップ支援 |
|
商工会議所・商工会 |
事業承継全般にわたる助言、情報提供、セミナー開催 |
専門家選びのポイント
様々な専門家が存在しますが、事業承継を円滑に進めるためには、下記のポイントに留意して専門家を選定することをお勧めします。
自社の課題と専門性がマッチしているか
事業承継の専門家はそれぞれ専門とする分野を持っています。
したがって、自社の課題を正しく認識したうえで得意とする業種・業界、規模、承継手法等の面で複数の候補先を比較検討し、自社の課題に最もマッチしている専門家を選ぶことが重要です。
手数料等の価格体系が明確で妥当か?
専門家に支払う手数料等の妥当性も重要なポイントです。
例えば、M&Aに関する業務を専門家に委託した場合、着手金、中間金、月額手数料、成功報酬等の費用が必要になると言われていますが、事業者によってその価格体系は大きく異なります。
最近では譲渡側企業からは費用を取らないケースや完全成功報酬型の事業者も増えています。
専門家の選定にあたってはその価格体系を十分理解したうえで納得感のある相手先を選ぶことが後々のトラブル回避にもつながります。
コミュニケーション能力が高いか?
いずれの専門家を選定したとしても、その担当者とは事業承継の初期段階からクロージング、場合によっては承継後も密接なやり取りを行うことになります。
ここで大切になるのがその担当者が持つコミュニケーション能力です。
知名度や価格だけで選定するのではなく担当者の人間性や応対、自社との相性等も含めて、高いコミュニケーション能力を持つ専門家を選ぶことが重要になります。
業界内に幅広いネットワークを保有しているか?
専門家はそれぞれ得意とする領域を持っていますが、事業承継に関連する専門分野は多岐に渡るためひとりで全てに対処できるケースは少ないのが実態です。
従って、業界内に幅広いネットワークを持ち必要な情報収集や他の専門家との連携をスムーズに行える専門家を選ぶことが、円滑な事業承継の実現につながります。
情報管理が徹底しているか?
専門家には、自社の機密情報や家族間の問題等他者には知られたくない情報を開示する必要が出てくる場合もあります。
また、M&Aの準備段階で万一自社社員に情報が漏洩した場合、社員の動揺やモチベーション低下等の弊害が生じるリスクもあります。
このため、専門家の選定にあたってはその情報管理体制を十分確認したうえで、安心して情報を開示できる相手を選ぶ必要があります。
事業承継における税理士との連携
税務・会計の専門家である税理士は、中小企業の経営者にとって身近な相談相手です。
特に顧問税理士は自社の財務状況や事業内容に精通しているため事業承継の専門家としても有力な選択肢となります。
税務上の承継対策
事業承継を行った場合、譲渡対価や付随費用等が生じるため、通常とは異なる複雑な会計処理が必要になります。
正しく税務申告を行い予期しない追徴課税を避けるためにも税理士への相談は必須となります。
事業承継における税理士との連携内容は主に3つあります。
-
節税対策の検討
-
相続税対策
-
節税対策の検討
会社や事業を売却して譲渡益が生じた場合、個人、法人ともに各種税金が発生します。
代表的な節税対策としては、役員退職金の活用や第三者割当増資等が挙げられますが、承継スキームや規模によって効果的な対策は異なります。
節税対策に詳しい税理士に相談することで適切なアドバイスが期待できます。
相続税対策
株式や事業用資産を後継者に承継した際は贈与税・相続税が発生し適切な税務手続きが必要になります。
一方、事業承継税制等の活用によりこれら税負担を軽減することが可能になります。
このような相続に関する税務処理においても税理士の専門知識を活用できます。
事業承継における弁護士との連携
事業承継には様々な利害関係者が関与するため当事者間の紛争リスクが生じます。
法的側面の紛争予防や利害関係の調整において弁護士は重要な役割を果たします。
事業承継のおける弁護士との連携内容は主に4つあります。
-
法的な問題の解決
-
契約書類の作成とチェック
-
紛争対応のサポート
-
法的な問題の解決
事業承継では、会社法、金融商品取引法、労働契約承継法他様々な法律で規定が定められており、対応を誤ると予期しないトラブルにつながります。
これら法的な問題の解決にあたっては弁護士の持つ専門性が必須となります。
また、法的リスクの洗い出しを目的に行われる法務ディユーディリジェンスも弁護士の専門領域となります。
契約書類の作成とチェック
M&Aで作成される代表的な契約書類には、
-
交渉開始時点で取り交わすNDA(秘密保持契約書)
-
M&Aの基本的事項を定めた基本合意書
-
最終的なクロージング段階で締結する最終契約書等
があります。
契約行為においては、記載事項の抜け漏れ、自社にとって不利になる条項、将来的な紛争リスクにつながる内容等が無い点を検証する必要があり、これには弁護士の持つ法的専門性が欠かせません。
紛争対応のサポート
M&Aの過程では、契約違反や株主間の対立等利害関係者間で様々な法的紛争が生じるリスクが生じます。
このような場合でも、法務ディユーディリジェンスや契約に立ち会った弁護士が適切なサポートを行うことで紛争の長期化を回避し、スムーズな解決につながることが期待できます。
事業承継におけるファイナンシャルプランナーとの連携
お金に関する幅広い知識を持ち、個人や企業の資金計画や資産運用等のアドバイスを行うファイナンシャルプランナーも事業承継における有力なアドバイザーとなります。
事業承継のおけるファイナンシャルプランナーとの連携内容は主に3つあります。
-
資金調達の計画
-
財務状況の分析
-
リスク管理のアドバイス
-
資金調達の計画
M&Aの場合譲受側だけでなく譲渡側にも、分散した株式や事業用資産の買い取り、相続税納税資金、第二創業や承継後の運転資金確保等に資金調達が必要になるケースがあります。
ファイナンシャルプランナーに相談することで適切な調達手段の選定や具体的な調達計画の立案ができるようになります。
財務状況の分析
事業承継を円滑に進めるための第一歩は、自社の経営課題や経営資源等を見える化し現状を正確に把握することです。
このうち財務面の現状分析において、ファイナンシャルプランナーの持つ専門性が活用できます。
さらに、不要資産の整理や滞留在庫の処分、余剰負債の返済等経営資源のスリム化を共に進める相手としても適任です。
リスク管理のアドバイス
クライアントである個人や企業のリスク管理もファイナンシャルプランナーの主要業務です。
偶発債務や簿外債務、資金繰り等M&Aで起こりうる金融面のリスクの事前洗い出しや、効果的な対策の提案を期待できます。
事業承継におけるM&Aアドバイザーとの連携
M&AアドバイザーとはM&Aに関する一連の手続きのアドバイスと実行を支援する専門事業者です。
通常M&Aアドバイザーは、その契約形態から仲介者とFA(ファイナンシャルアドバイザー)に分かれます。
そのため選定にあたっては、各々の違いを正しく認識することが重要になります。
|
|
契約形態 |
特徴 |
|
仲介者 |
譲渡側、譲受側双方と契約 |
両者の意思疎通が容易に行える |
|
FA |
譲渡側、譲受側どちらか一方と契約 |
契約者の利益に忠実な助言、支援が期待できる |
なお、中小企業のM&Aにおいては、支払い余力の関係でFAよりも仲介者が多く用いられる傾向があります。(支払い余力に関しては、譲渡側、譲受側双方から手数料を頂戴する場合と、どちらか一方からしか手数料を頂戴しない場合とで、M&Aアドバイザーが受け取る手数料は異なります。
例えば、譲渡側から手数料を10百万頂戴し、譲受側からも10百万を頂戴する場合、仲介の場合、20百万となり、FAの場合、10百万となる。そのため、FAの場合、一定規模以上であることが好ましく、仲介の場合、双方から頂戴できるため一定規模ではない場合でも対応できることもあります。
そのため費用負担が仲介の方が少なくとも支援ができる業者が多いことが傾向としてあります。)
M&Aアドバイザーとの連携内容は主に4つあります。
-
適切な取引相手の選定
-
評価額の算定
-
交渉戦略の立案
-
適切な取引相手の選定
M&Aを進めるうえで、譲受企業の選定(マッチング)は非常に重要な工程になります。
M&Aアドバイザーは保有するネットワークや経験を活かして、クライアントの条件に見合う適切な相手先の選定を行います。
また、最近ではM&Aプラットフォームと呼ばれるインターネット上のマッチングサービスも急速に浸透しつつあり、M&Aプラットフォームを利用するケースも増えています。
評価額の算定
譲渡企業にとって自社の評価額がいくらになるのかは、最大の関心事のひとつです。
企業価値の評価手法には、簿価純資産法、時価純資産法、類似会社比較法等、多様な手法があります。
いずれも高度なファイナンシャルの知識が必要になり、ケース毎に適切な手法は異なるため、専門家であるM&Aアドバイザーに相談する場合が大半になります。
なお、実際の中小M&Aの現場では、時価純資産に2~5年分の営業利益を加算する簡易的な手法が用いられるケースも多く見られます。
交渉戦略の立案
M&Aでは相手側企業と譲渡条件の交渉が行われますが、有能なM&Aアドバイザーの活用により、交渉を有利に進められるようになります。
M&Aアドバイザーは譲渡額を含めた譲渡条件を少しでも有利にするため、
-
譲渡企業の持つ技術力やブランド力等の無形資産のアピール策
-
譲渡条件の優先順位付け
等の交渉戦略を立案し実行します。
専門家と協力し進める事業承継の流れ
事業承継は、人(経営)、資産、知的資産と検討すべき項目が多岐に渡り、一定の時間を要する取り組みになります。
このため、円滑な事業承継を実現するためには、十分な準備期間を確保し、早い段階から専門家の支援を仰いで二人三脚で進めていくことが不可欠です。
|
人(経営)の承継 |
資産の承継 |
|
経営権 |
株式 |
|
知的資産の承継 |
|
|
経営理念 ・従業員の技術や技能 ・ノウハウ |
|
事業承継計画の策定
事業承継を進めるにあたっては、自社や自社を取り巻く状況を整理したうえで、将来を見据え、事業承継の時期や具体的な目標、課題等を整理した事業承継計画を策定することが重要なステップとなります。
これまで事業計画書類をあまり作ってこなかった経営者にとって、専門家の活用は実効性ある計画書策定のための有力な手段となります。
承継者の選定と育成
後継者に対し経営に必要な能力や知識を身に付けてもらうためには、計画的な教育を施す必要があります。
後継者教育には、社内の業務に従事させながら、実践的な育成を行う社内教育と自社外での勤務や外部セミナー活用等の社外教育があります。
事業承継の現場では、育成計画の策定や社外教育等を専門家の力を借りながら進めるケースも多く見られます。
事業継続のための戦略立案
社会経済が速いスピードで大きく変化する現在では、事業承継後の後継者には、新たな視点で事業の見直しを行いながら、次の成長ステージに進んでいくことが求められます。
また、M&Aにより事業の一部を売却した後、既存事業の再構築や新事業への挑戦に取り組む場合は新たな事業戦略が必要になります。
事業承継で支援を仰いだ専門家は、自社の内情もよく理解しています。
このような承継後の事業展開においても、戦略コンサルタントとして継続活用するメリットは大きいと言えるでしょう。
専門家活用時の注意点
ここまでM&Aを含む事業承継において、専門家の活用が円滑な遂行に欠かせない点を解説してきました。
専門家を効果的に活用するためには以下に解説する注意点を意識することが大切になります。
明確な目標設定と期待値の調整
事業承継の目的はその企業の内部事情や事業環境によって異なりますが、大切なのは事業承継計画を策定する段階で、その目標を具体化し優先順位をつけることです。
そして、事業承継の時期や譲渡額・承継後の売上利益等については、可能な限り定量的な目標値を定め、これを専門家と共有することが大変重要です。
また、専門家に期待する支援内容や支援期間、介入の程度、費用等については初期段階で十分話し合い、納得感をもって支援を依頼することが円滑な事業承継の遂行につながります。
コミュニケーションの重要性
専門家として個人の士業等に委託した場合はもちろんですが、大手仲介会社や法人組織に委託したとしても、最終的に自社を担当するのは1名~数名の担当者になります。
この担当者に対しては、場合によっては家族間の問題や自社にとって不利な情報等も包み隠さず伝える必要が出ます。
このため、担当者との間では十分なコミュニケーションをとり、お互い信頼関係をもって進めることが重要になります。
担当者とは頻繁に会話する機会を設け、計画通りに進まない場合も相談のうえ計画を見直していくことを心がけましょう。
継続的な関係性の構築
M&Aがクロージングを迎えた後も、譲渡側企業は譲受側企業の円滑な引継ぎ等に対して誠実に対応することが求められます。
また、譲渡資金を活用して新たな事業展開を図る場合や、後継経営者が経営改善に取り組む場合には、事業戦略やビジネスプランの検討が必要になります。
事業承継の専門家は総じて経営全般に関する知識や支援経験を持つ場合が多いです。
このような事業承継後の様々な局面でも頼りになるアドバイザーとしての働きが期待できます。そのため、事業承継を共に進めてきた専門家とは、承継後も継続的な関係を維持することをおすすめします。
事業承継の初期相談は日本提携支援へ
事業承継に関する専門家について解説してきました。
事業承継には多くのステップがあり専門知識も必要になるため、早い段階から専門家の支援を仰ぎ、計画的に進めることが重要になります。
日本提携支援には豊富な実績、経験のある専門家が多数在籍していますので、事業承継に関する専門家の活用方法や留意点について具体的なアドバイスが可能です。
当社では相談者の方から手数料をいただいておりませんので費用面でも安心してご相談いただけます。お気軽にお問合せください。