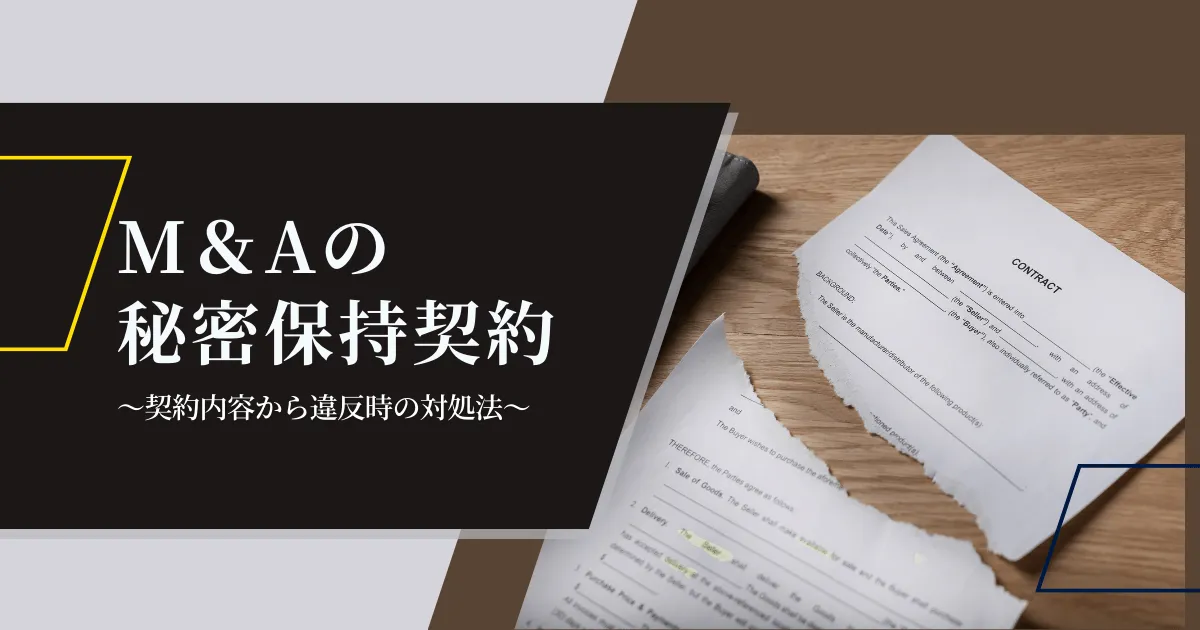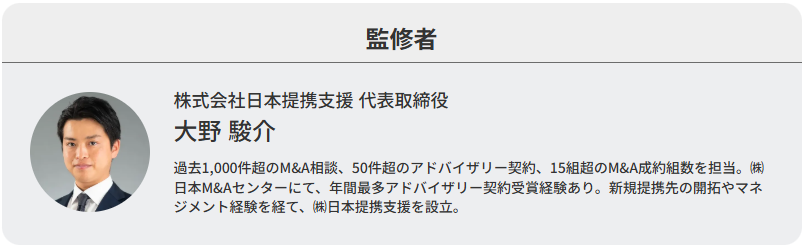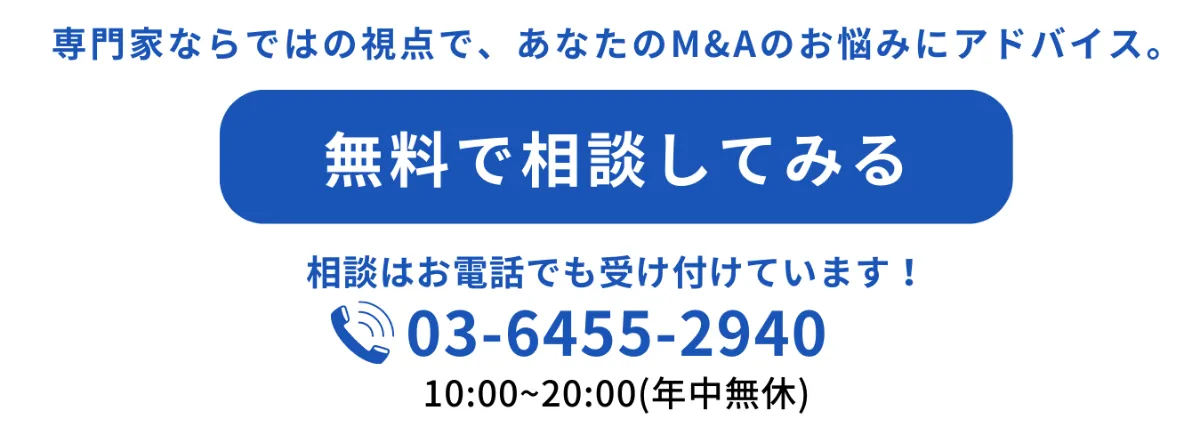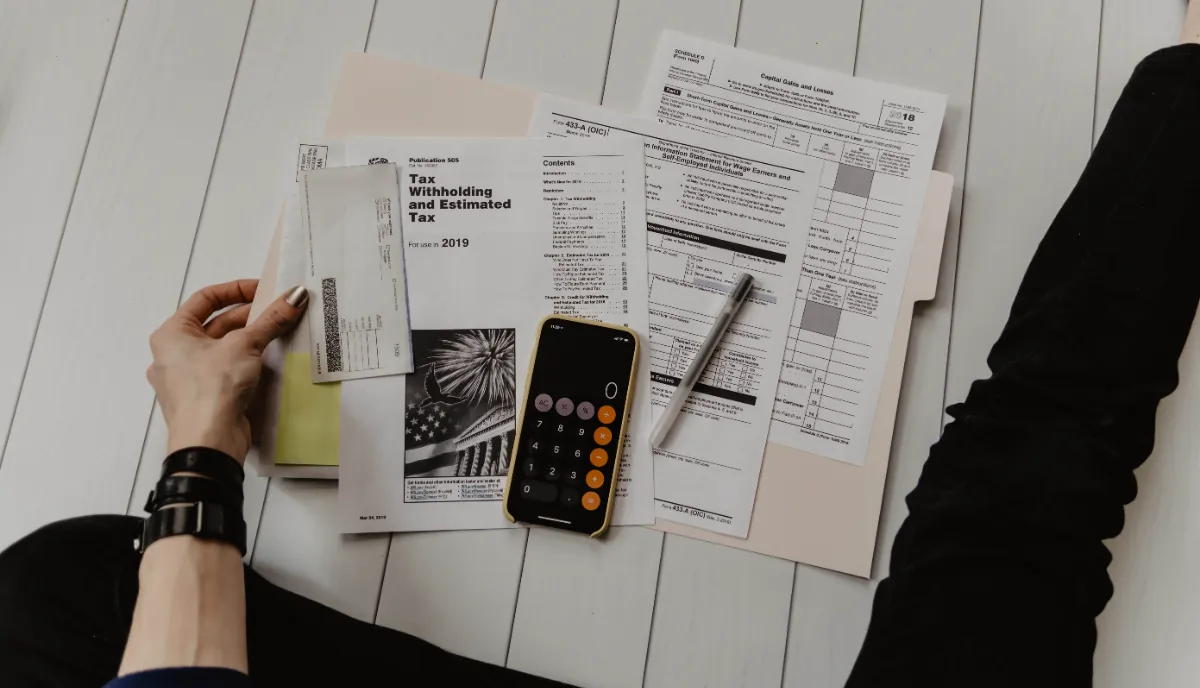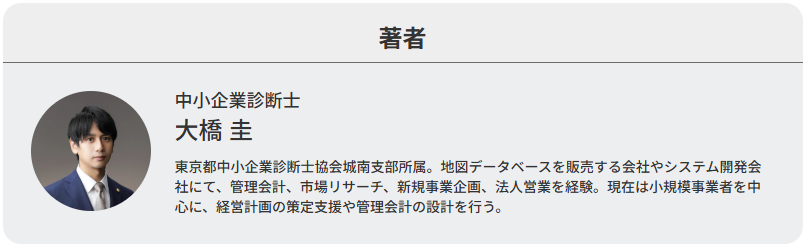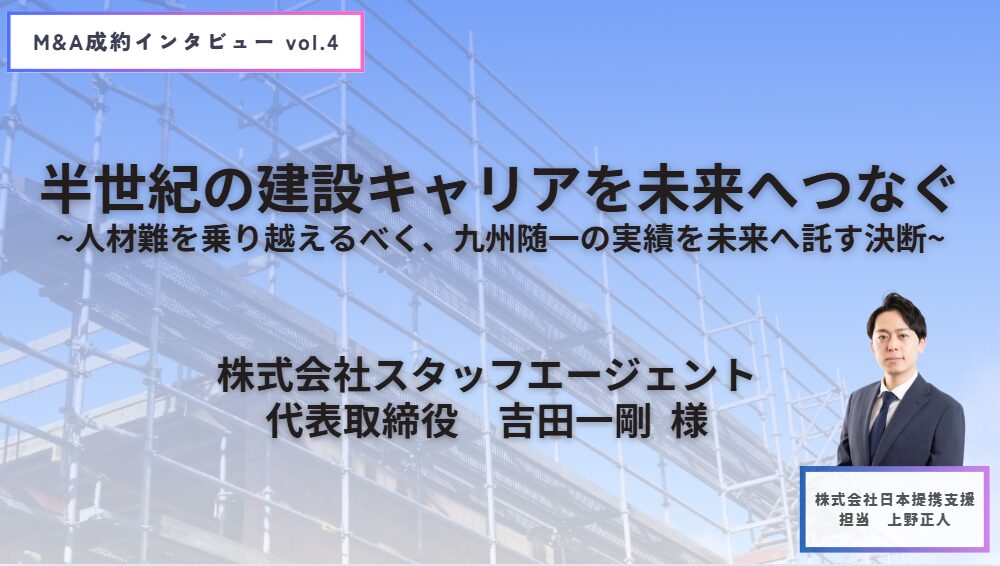M&Aを検討する際、M&A仲介会社や買い手の候補に対して、売却希望条件や顧客の情報、財務情報など、多くの情報を開示します。
これらは基本的に、ホームページ等で公開していない非公開の情報であり、社内外にM&Aの検討状況が漏れてしまうと様々なトラブルを引き起こす可能性があります。
そのため、売り手・買い手双方が授受する情報の取り扱いについては、契約にて定めておくことが重要です。
本記事では、M&Aの「秘密保持契約書(NDA)」の内容について解説していきます。
M&Aにおける秘密保持契約の重要性
M&Aでは、企業内部の情報を提供するため、情報の管理がとても重要です。
この章では、M&Aにおける情報の取り扱いや、秘密保持契約を締結する目的について解説します。
M&Aプロセスにおける情報の取り扱い
M&Aでは、主に売り手企業が買い手候補の企業やM&A仲介会社などに対して、財務諸表、保有する技術、顧客、今後の事業展開など会社内部に踏み込んだ情報を開示していきます。
これらの重要な情報をやり取りする前に締結されるのが秘密保持契約です。
具体的には、以下のようなタイミングで締結します。
-
M&A仲介会社やM&Aアドバイザーに対して、情報を開示する際
-
ネームクリア後に、買い手候補に対して情報を開示する際
-
デューディリジェンス(買収調査)を実施する前
秘密保持契約を交わすことで、情報の取り扱いに対する双方の義務、義務違反した場合の対応が明確になり、情報漏洩のリスクを低減できます。
秘密保持契約の目的
秘密保持契約は、秘密情報について目的以外の利用を禁止し、第三者に開示しないよう、情報管理に関わる取り決めをする契約書です。
英語では、「Non-Disclosure Agreement」であることから、頭文字を取ってNDAとも呼ばれます。
M&Aにおける秘密保持契約の目的は、秘密情報や、関与する各当事者間で守秘義務を確立することであり、M&Aのプロセス中に情報漏洩や不正競争を防ぐためにとても重要です。
また、秘密保持契約を締結することにより、売り手企業の業績や戦略を評価するために必要な情報の提供が可能になるため、デューディリジェンスのプロセスをスムーズに進めることも目的の一つです。
以上の点から、秘密保持契約は、M&Aを検討する際に安全性と円滑な進行を確保するために欠かせない重要な契約です。
秘密保持契約を締結しない場合のリスク
秘密保持契約を締結しない場合には、いくつかのリスクを抱えたままM&Aの検討を進めることになります。
-
情報漏洩リスク
-
評価精度低下リスク
-
法的保護不足リスク
情報漏洩リスク
まず、秘密情報の開示範囲やM&Aを検討する目的以外の利用について制限がされていないことから、情報が漏洩するリスクがあります。
特に売り手の立場として開示した情報には、顧客情報、技術に関する情報が含まれるので注意が必要です。
自社の競争の源泉である強みに関する情報が漏洩すれば、市場において不正競争が生じますし、取引先情報が流出するようなことがあれば、顧客との取引に影響を及ぼします。
最終的には、企業価値が毀損し、売却価額が低下する可能性があります。
評価制度低下リスク
また、デューディリジェンスのプロセスにおいても問題が生じます。
企業の業績やリスクを評価するために開示できる情報が不足し、企業評価の精度を高めることができません。
事前に得られる情報が不足することで、後の段階で予期せぬ問題が浮上し、取引の進行が困難になる、またはM&Aの検討自体が中止される可能性があります。
法的保護不足リスク
さらに、法的な保護が不十分になります。
秘密保持契約は法的な拘束力を持つ文書のため、情報漏洩が発生した際は、契約書の内容に則り、損害賠償請求や差止請求を行うことができます。
一方、契約が存在しない場合は、情報漏洩元への罰則について定めがないため、トラブルへの対応が難航するリスクがあります。
これらのリスクを低減するためにも、M&Aを検討する際は、秘密保持契約の締結が必須です。
秘密保持契約の主な内容
M&Aにおける秘密保持契約に盛り込むべき、一般的な条項について解説します。
これらの条項が含まれているか、内容として適切なものになっているかご自身の目でも確認するようにすることを推奨します。
-
目的
-
秘密情報の定義
-
目的外使用の禁止
-
開示範囲
-
有効期間
-
返却・廃棄
-
準拠法
-
管轄裁判所
1.目的
まず始めに秘密保持契約の目的を明確にします。
目的を明確にすることで、秘密情報の定義や、情報の使用範囲などの設定が可能になります。
2.秘密情報の定義
秘密保持契約では、開示する情報のうち「何が秘密情報にあたるのか」を定義しておく必要があります。
主な情報の開示者となる売り手の立場としては、情報漏洩のリスクを低減するために、「紙、電子媒体、電子メール、口頭等、提供の媒体および手段を問わず、開示側の当事者から受領側の当事者に開示する、一切の情報をいう。」といった形で、なるべく幅広く定義することが一般的です。
一方、情報の受領者となる買い手にとっては、義務を負う情報の範囲を狭くするため、開示に先立って受領者が知っていた情報や公知の情報等は、秘密情報の例外として規定します。
秘密情報を幅広く定義すると、情報の開示者側が有利になり、狭く定義した場合は、情報の受領者側が有利になります。
双方協議の上、適切なバランスで定義をします。
3.目的外使用の禁止
開示する情報には、技術情報や調達先、販売先など営業上、重要な情報が含まれますので、M&A検討の目的以外で使用することは禁止します。
秘密情報を保護し、情報を受け取る側の不正な利用や情報漏洩を防止するために重要な条項です。
4.開示範囲
情報の受領側が、秘密情報を不要に第三者に開示することを禁止します。
ただし、M&Aでは弁護士や税理士、金融機関等、多くの関係者が関わりますので、あらかじめ判明している開示先は明記しておきます。
契約時点で明記できない開示先がある場合は、事前に書面等で合意を得ることで開示できるよう、定めておくとよいでしょう。
また、第三者に情報を開示する際は、情報の開示元が開示先の義務違反についても責任を負うよう定めます。
5.有効期間
最終的にM&Aの成立に至らなかったとしても、開示した情報については適切に管理してもらう必要があるため、情報を保護する有効期間を定めます。
情報の特性により有効期間は異なりますが、1~3年前後で締結することが一般的です。
また、損害賠償や差止請求等は、必要に応じて有効期間が満了した後も効力を有するよう定めます。
6.返却・廃棄
M&Aの検討が終了した後は、秘密情報の返還および廃棄を義務づける条項です。
情報を開示したとしても、交渉の結果、M&Aの成約に至らないこともあります。
また、成約に至らなかった相手が、秘密情報を保持したままの状態であることは望ましくありません。
検討が終了した後は、すみやかに情報の廃棄、または返却をしてもらうよう、契約で定めます。
より厳密に管理したい場合は、廃棄の事実を証明する文書の提出を求めるケースもあります。
目的が達成した後の情報の取り扱いを定めておくことで、情報漏洩のリスクを低減できますので、有効期間と合わせて検討しましょう。
7.準拠法
売り手、買い手、関係者が国内の法人・個人である場合は、日本法が適用されます。
一方、関係者に海外の法人・個人が関わる場合は準拠法の規定が必要です。
8.管轄裁判所
実際に裁判になった際のために、契約書等の書面で定めておくことで第一審に限り専属的合意管轄裁判所を決めておくことができます。
裁判所への移動は、弁護士費用や交通費などのコストがかかるので、双方の公平性を鑑み、適切な裁判所を指定します。
なかなか合意にいたらない場合は、被告側の本店所在地を管轄する地方裁判所を定めるなど、被告地主義を採用することも有効です。
違反時の対処方法
秘密保持契約を締結したとしても、情報の受領者が義務違反をする、または開示先の第三者から情報が漏洩する、といったリスクがなくなるわけではありません。
義務違反をした際の対応については、あらかじめ条項で定めておきます。
主な対処方法は、以下になります。
-
損害賠償請求
-
差止請求
-
違約金
損害賠償請求
損害賠償請求は、秘密保持契約にて定められた義務を違反することによって、他の契約当事者に損害が発生した場合の罰則です。
違反が起きた場合にその被害を回復するために、違反行為をした当事者に対して金銭的な補償を求めます。
損害は、情報漏洩によって発生した利益の減少などの直接的な損害のほか、弁護士費用などの法的費用、漏洩した情報を回収するための費用などが含まれます。
情報の受領者として、損害の範囲を狭くしたい場合には、「直接生じた損害」に限定することも検討します。
差止請求
差止請求は、実際に発生した損害を補填する目的の損害賠償とは異なり、違反行為そのものを阻止し、損害を未然に防ぐ手段です。
あらかじめ秘密保持契約に定めておくことで、秘密情報の不正使用などが発生した場合に、情報の漏洩元に対して、情報の使用停止を命じることができます。
損害賠償請求も差止請求も、違反行為が発生した場合の対応をあらかじめ条項として定めておくことで、スムーズに対応を行うことができます。
違約金
違約金の存在は損害賠償請求において重要な位置を占めます。
秘密保持契約に違反した場合に設ける違約金は、立証が困難な損害額を省力化する手段です。
設定の目的
違約金は、予め損害額を推測し、それを基に設定されます。
その価格は、損害を適切に補填する範囲内にあるべきです。
設定のメリット
違約金の設定は、秘密保持契約の違反があった際に明確な利点を持ちます。
すなわち、既に決定している違約金の支払いを要求することで、損害賠償額の算定や立証の労力を減らすことができます。
設定のデメリット
しかし、事前に損害額を推定することは困難という欠点も伴います。
加えて、情報の受け取り手にとっては不利な条項となり得るため、秘密保持契約における違約金の設定は、一般的にはあまり行われていません。
当事者間の交渉と合意のプロセス
秘密保持契約を締結する際、双方にとって不利な条項となっていないか確認し、必要に応じて修正の交渉を行います。
秘密保持契約の締結する際のプロセスは4つにまとめることが出来ます。
-
交渉の準備
-
草案の作成と確認
-
条項の詳細な検討と交渉
-
修正と合意形成
(1)交渉の準備
交渉に入る前に、秘密情報の範囲、保護期間などについて、自社の考え方を明確にします。
(2)草案の作成と確認
秘密保持契約の草案を作成し、相手方に提出します。
草案を受け取った側は内容について一方的に不利な内容になっていないか、不明確な内容はないかを確認します。
(3)条項の詳細な検討と交渉
秘密情報の定義や範囲、目的外使用の禁止、有効期間、違反時の法的措置など、各条項について詳細な検討を行います。
修正が必要な場合は、自社の考えを提示し、交渉を行います。
(4)修正と合意形成
意見の相違点を議論し、必要な修正や調整を行った上で、双方が合意し、契約内容が確定します。
相互の利益を考慮し、専門家の助言や法的なサポートを受けながら、公平かつバランスの取れた契約を目指しましょう。
秘密保持契約のメリット
秘密保持契約を締結することで、以下のような効果があります。
情報管理への意識向上
情報漏洩を防止するためには、「どの情報が秘密情報か」を明確にすることが第一歩です。
秘密情報が不明確なままだと、該当する情報がわからず情報管理がずさんになるからです。
秘密保持契約では、該当する秘密情報と開示可能な範囲が明確になることから、関係者の情報管理への意識を高めることに役立ちます。
また、義務を怠った際の罰則が契約に定められることから、情報漏洩の抑止力にもなります。
スムーズなM&Aプロセスの実現
秘密保持契約を締結しない場合は、開示できる情報に制限が出るほか、情報漏洩時は契約書という拠り所がないため、交渉が難航します。
一方、秘密保持契約を締結しておくことで、売り手、買い手が正しい情報を共有した上で、交渉を行うことができます。
また、万が一、情報漏洩をした際も、契約内で定められた手法に則り、手続きを進めるため、スムーズなトラブルへの対応が可能になります。
M&Aの秘密保持契約でお困りなら日本提携支援に相談
本記事では、秘密保持契約の条項や、作成のポイントについて解説してきました。
M&Aを検討する際は、重要な情報をやり取りするため、秘密保持契約の締結は欠かすことができません。
一方、自社だけでは、不利な契約になっていないかを判断するのは難しいケースがあるため、専門家のアドバイスをもらうことが有効です。
日本提携支援には、豊富な経験を保有するアドバイザーが多数在籍しており、契約書の内容やプロセスについてアドバイスが可能です。
当社では相談者の方からは手数料をいただいておりませんので、お気軽に日本提携支援にお問い合わせください。