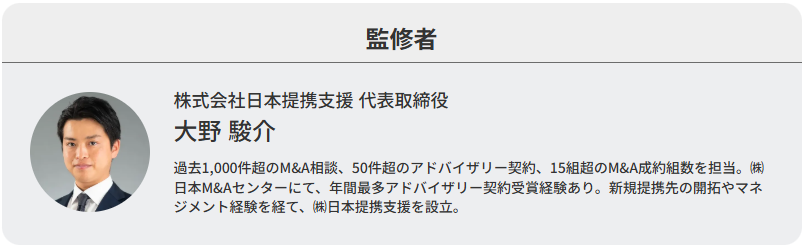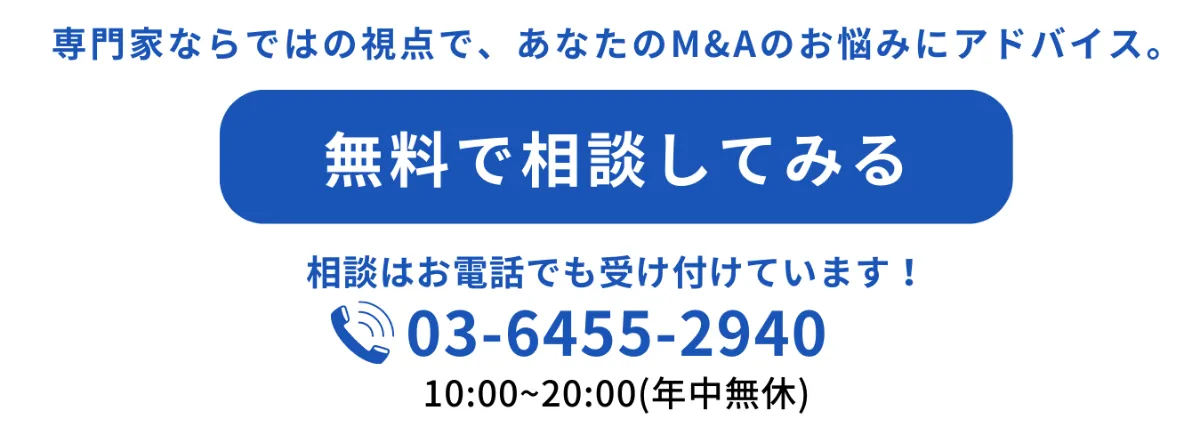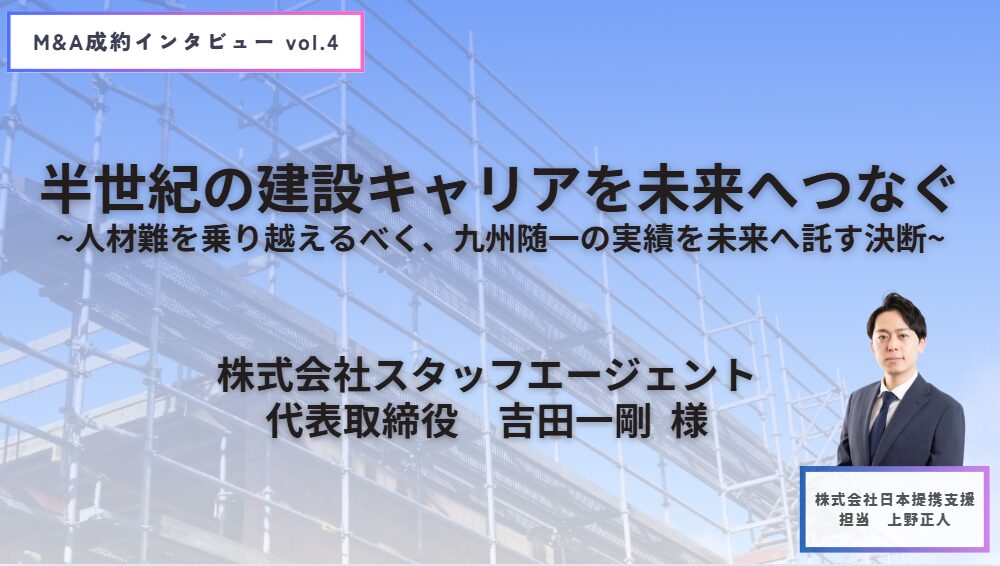経営者の高齢化が進む中、近年中小企業においても事業承継の手段としてM&Aを検討する経営者が急速に増加しています。
実際、中小M&Aの実施件数も右肩上がりで増加しており、中小企業庁「中小M&A推進計画」では、足下では年間3~4千件程度実施されていると分析されています。
また、M&Aに対するイメージも大幅に改善しており、10年前と比較すると譲受、譲渡ともにプラスイメージがマイナスイメージを大きく上回っていることが確認できます。
このように、中小企業にとってM&Aは事業承継の手段として身近なものになりつつあるのが現状です。
本コラムでは、中小企業のM&A手法として使われることの多い事業売却を取り上げ、事例を踏まえながらその特徴や進め方のポイントについて解説していきます。
事業売却の意義と基本的な流れ
事業売却の目的とは?
事業売却は事業譲渡と同義でとらえられ、会社の事業の一部、あるいは全部を第三者に売却するM&A手法です。
会社売却と混同されることも多いのですが、株式譲渡に代表される会社売却は現金等を対価として自社の株式を買い手に渡すことで会社の経営権そのものを譲渡するものであり、譲渡する対象が大きく異なる点に注意が必要です。
|
|
譲渡の対象 |
主な特徴 |
|
事業売却 |
事業の一部または全部 |
特定の事業を指定して売却できる |
|
会社売却 |
株式の一部または全部 |
手続きが簡素で迅速に進められる |
事業売却はこのような特徴を持ちますので以下の目的で選択されるケースが多くなります。
-
不採算部門を切り離し、主力事業に集中することで経営の効率化を図る
-
売却後も会社と従業員をそのまま存続させる
-
売却益を得て負債の返済や新事業への投資に回す
基本的な事業売却のプロセス
事業売却の基本的なプロセスは他のM&A手法と大きく異なることはなく、以下の手順に沿って進めていくのが一般的です。
ステップ1:事前準備(支援機関への相談)
ステップ2:仲介者・アドバイザーの選定と契約
ステップ3:バリュエーション(企業・事業価値評価)
ステップ4:マッチング(譲渡候補先企業の選定)
ステップ5:交 渉
ステップ6:基本合意の締結
ステップ7:デューデリジェンス(買収監査)
ステップ8:最終契約の締結
ステップ9:クロージング
事業売却を含むM&Aでは、検討すべき項目が多岐にわたり高度な専門知識を必要とする場面も発生します。
自社人材だけでこのような課題に対処することが困難な中小企業にとって、早い段階で支援機関に相談することが円滑に進めるポイントとなります。
また、事業売却ならではの留意事項として、一定の条件を除いては原則株主総会の特別決議により株主の3分の2以上の信任を得る必要がある点には注意する必要があります。
売却を考えるタイミング
事業売却を考えるきっかけとしては、経営者自身の気力・体力の衰えや所属する商工会・商工会議所や顧問税理士などから進められる場合などが挙げられますが、有利な売却条件を得るためには、そのタイミングも重要になってきます。
一般的には、自社の業績が比較的良い時、業界の景気が上向きの時や業界再編が起こっている時などは、好条件で売却できる可能性が高くなります。
いずれにしろ、適切なタイミングで売却を実現するためには、売却の目的を明確化し早期から着手する、自社の事業の磨き上げに注力する、業界動向を注視する、といった取り組みが大切になります。
事業価値の評価方法
バリュエーション手法の選択
バリュエーションとは事業売却の過程において、売却される事業の価値を定量的に評価する手続きであり、最終的な譲渡額の目安となる指標になります。
その手法は、コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチに分類されますが、ケース毎に適切な手法は異なるため、支援機関に相談のうえ最適な手法を選択することがポイントとなります。
|
バリュエーション手法 |
主な特徴 |
|
コストアプローチ |
BS上の現在の純資産の価値に着目 |
|
マーケットアプローチ |
株式市場における価値評価に着目 |
|
インカムアプローチ |
将来期待される収益性に着目 |
具体的な評価方法とその計算式
中小M&Aで用いられることの多い手法として、コストアプローチから「簿価純資産法」と「時価純資産法(修正簿価純資産法)」、マーケットアプローチから「類似会社比較法(マルチプル法)」を取り上げて、その簡易的な計算式を解説します。
-
簿価純資産法
貸借対照表の資産と負債の差分として求められる簿価純資産を事業価値とする方法です。
-
時価純資産法(修正簿価純資産法)
貸借対照表の資産と負債をそれぞれ時価評価したうえでその差分である時価純資産を事業価値とする方法です。時価評価の対象となる項目の一例として、売掛金、棚卸資産、有価証券、保有土地、賞与引当金、退職給与引当金などが挙げられます。
-
類似会社比較法(マルチプル法)
自社と類似の上場企業の企業価値(EV)及び財務指標から求めた評価指標倍率(企業価値/評価指標)を基にして、自社の事業価値を算出する方法です。
中小M&Aにて評価指標値として用いられることの多いEBITDA(「償却前利益」とも呼ばれ簡易的に「営業利益+減価償却費」とするケースが多い)による計算式は次の通りです。
なお、類似企業比較法については、参考とする類似企業の選択や何を評価指標とするかによっても最終的な事業価値が大きく異なる可能性がある点には注意が必要です。
価値評価の難しさと解決策
譲渡企業にとって自社の評価額がいくらになるのかは最大の関心事のひとつですが、評価にあたってはケース毎に適切な手法が異なります。
また、高度な会計やファイナンシャルの知識が必要になるため、取り組みの初期段階から専門家の支援を仰ぐことが大切になります。
なお、実際の中小M&Aの現場では、時価純資産に2~5年分の営業利益を加算する簡易的な手法が用いられるケースも多く見られますので、このあたりも専門家に相談の上、自社の状況にマッチした最適な方法を選択することをお勧めします。
事業売却の法的手続き
必要な契約書類の概要
事業売却にあたって必要となる契約書類は他のM&A手法と大きく異なることはなく、社外専門家から支援を受ける際に締結する「仲介・アドバイザリー契約書」、交渉開始時点で取り交わす「NDA(秘密保持契約書)」、M&Aの基本的事項を定めた「基本合意書」などが必要となります。
さらに、最終的なクロージングの段階で締結するのが「事業売却(事業譲渡)契約書」となり、主に下記内容が記載されます。
-
譲渡対象(何を譲渡するか)
-
譲渡時期(いつ譲渡するか)
-
譲渡対価(代金をいくらにするか)
-
支払時期と方法(譲渡対価をいつどのような方法で支払うか)
-
その他制約事項等
売却に伴う税金の対策
事業売却を行った場合、売り手側には「法人税」と「消費税」が課されます。
-
法人税の考え方
売却額が譲渡する資産と負債の簿価よりも大きい場合、売却益が発生しこれに対して法人税等(法人住民税、事業税を含む)が発生します。
この法人税等は当該事業年度における事業上の損益と通算されます。
例えば、売却額が1億円、譲渡対象の資産と負債の簿価が6,000万円の場合、売却益は4,000万円となり、法人税等の実効税率を30%とした場合の納税額は1,200万円となります。
-
消費税の考え方
売却した資産から土地や有価証券などの非課税対象資産を除いた課税対象資産に対して10%の消費税が徴収されます。これは、売却による利益に対して課税されるものではないため、事業売却により赤字が生じたとしても課税される点には注意が必要です。
例えば、課税対象資産が5,000万円の場合の消費税の納税額は500万円となります。
法律家との協働の重要性
事業売却では、他のM&A手法同様、会社法、金融商品取引法、労働契約承継法他様々な法律で規定が定められているため、対応を誤ると予期しないトラブルにつながります。
これら法的な問題の解決にあたっては弁護士等が持つの法的専門性が必須となります。
また、法的リスクの洗い出しを目的に行われる法務デューデリジェンスも弁護士の専門領域となります。
他にも、M&Aの過程では契約違反や株主間の対立等利害関係者間で様々な法的紛争が生じるリスクが生じます。
このような場合でも、弁護士の適切なサポートを受けることで、紛争の長期化回避やスムーズな解決が期待できます。
適切な事業売却先の選び方
事業売却を検討する経営者にとって、適切な売却先を選定すること(マッチング)は極めて重要なテーマですが、自身の人脈や事業上の関係者から売却先を探すのでは限界があります。中小M&Aでは次に挙げる専門機関に相談の上、売却先を探すのが一般的です。
-
M&Aブローカー(仲介専門事業者)
-
メインバンクを始めとした金融機関
-
顧問税理士や公認会計士
また、近年公的支援機関もM&Aへの対応を強化しており、身近な商工会議所・商工会、事業承継・引継ぎ支援センターなどに相談するところから始める経営者も多く見られます。
その他、M&Aプラットフォームと呼ばれるインターネット上のシステムを活用してオンラインで譲渡側・譲受側のマッチングの場を提供するサービスも急速に浸透しつつあり、多数の中小企業も利用しています。
M&Aブローカーの利用
M&Aブローカーとは、M&Aの専門家として仲介サービスを提供する事業者のことで、通常その契約形態から仲介者とFA(ファイナンシャルアドバイザー)に分かれます。
|
|
契約形態 |
特徴 |
|
仲介者 |
譲渡側、譲受側双方と契約 |
両者の意思疎通が容易に行える |
|
FA |
譲渡側、譲受側どちらか一方と契約 |
契約者の利益に忠実な助言、支援が期待できる |
M&Aブローカーの選定にあたっては各々の特徴を把握したうえで、得意とする業種や規模、サービス範囲と価格の妥当性、専門性の高さ、経験の豊富さなどをチェックし、自社の課題に適した相手先を選択することが重要になります。
買い手との交渉術
事業売却の際、売却額の確定には買い手側との交渉が必須です。
有利な条件を勝ち取るためには以下の3つのポイントに注意し、戦略的な交渉を進めることが重要です。
自社の強みとなる無形資産のアピール
会社には財務諸表からは見えない無形資産が存在します。
これは優秀な従業員、高い技術力、販売網、取引先との関係、地域の知名度、信用力、許認可、ノウハウなどを含みます。
買い手にとって魅力的な無形資産を明らかにし、これらを効果的にアピールすることが、好条件を引き出す一助となります。
業績が悪い場合の改善策と見通しの提示
赤字や債務超過で経営状況が良くない場合でも、その原因を明示し、具体的な改善策に取り組む姿勢が求められます。
また、中期計画などを通じて将来のビジョンを示すことも有効です。
妥協可能な条件の明示と歩み寄りの姿勢
事業売却は相手との交渉が基本となります。
全ての要望が受け入れられることは少ないです。
売却価格、社名・ブランド名の存続、従業員の継続雇用など、売却条件には優先順位をつけ、妥協できる部分とできない部分を整理しましょう。
そして、歩み寄る姿勢をもって交渉に臨むことが大切です。
売却後の移行期間の管理
引き継ぎ期間とその重要性
無事クロージングを迎え事業売却が終了した後も、売却側経営者はPMI(Post Merger Integration)と呼ばれるM&A後の事業統合作業において重要な役割を担います。
中小企業庁「中小PMIガイドライン」ではPMIには概ね1年間の期間を要すると言われており、この間、売却側経営者は円滑な事業引継ぎ等の実現に向けに、買い手側企業と双方向のコミュニケーションをとり誠実に対応する必要が生じます。
特に、最終契約において具体的な協力義務等が定められている場合は、これを果たすことが求められます。
買い手との協働のポイント
「中小企業白書」2023年版によれば、M&Aの買い手側企業が抱く最大の障壁は「相手先従業員の理解が得られるかの不安」で、回答者の半数以上がこれに該当しました。
また、3割以上が「期待する効果が得られるかがわからない」と回答しています。
買い手側企業は、組織の円滑な融合や期待効果の早期発現を懸念していると見られます。
これらの懸念を払拭し円滑な引き継ぎを実現するため、事業売却後の統合管理 (PMI) において、売却側の経営者は以下のポイントに重点を置くことが重要です。
関係者間の信頼関係の構築
買い手側企業の経営者との信頼関係を構築するため、適切なコミュニケーションの機会を設け、相互理解を深めることが求められます。
さらに、売却対象事業に携わる従業員が環境変化による不安感や不信感を抱くことがあるため、個別面談や説明会を開催し、継続的なコミュニケーションを行うことが重要です。
売上拡大につながる売上シナジーの実現
事業売却後、双方の経営資源を活用することで製品・サービスの開発や高付加価値化、販路拡大などを目指すべきです。
これにより売上拡大につながるシナジー効果を獲得します。
費用削減につながるコストシナジーの実現
事業売却は売上だけでなくコスト面のシナジー効果も実現可能です。
生産現場の改善、生産体制の見直し、調達先や在庫管理方法の見直し、管理・販売拠点の統廃合、販促活動や広告宣伝、間接業務の見直しなど、事業売却によって広範囲に及ぶコスト削減が可能となります。
売却側の経営者は、これらの取り組みを買い手側企業が進めやすいように支援することが求められます。
事業売却後の生活設計
事業売却後の経営者の身の振り方は主に以下の4ケースに分類されます。
-
役員として継続して経営に関与する
-
売却資金をもとに新規起業する
-
別の企業に就職する
-
完全にリタイアしセカンドライフを送る
2019年「中小企業白書」では、引退した経営者の現在の雇用形態が分析されており、これによると、約四分の一が無職である一方、会社・団体などの役員が4割強、何らかの形態で雇用契約を結んで働いている方が2割強となっています。
事業売却後の生活設計は経営者自身の年齢や健康状態、家庭環境など様々な要因が関係しますので、正にケースバイケースである点が確認できます。
いずれを選択するにしろ、早い段階で事業売却後のありたい姿を明確にして計画的に進めることがその後の生活の満足度向上につながると言えるでしょう。
事業売却の成功例と失敗例
成功事例の分析
中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」には、事業売却を含む多数の中小M&A事例が掲載されています。ここから事業売却に該当するケースを中心に、実際のM&Aの現場でよく見られる成功事例をいくつか紹介します。
事例1:技術力や商圏の評価によるM&A成功
事業規模や財務状況からM&Aは難しいと考えていたが、公的機関に相談したところ、予想に反し技術力や商圏を評価され成功に至ったケース。
事例2:廃業の危機からの事業引継ぎ
高齢の個人事業主で、廃業を考えていたが、公的機関に相談したところ、同業で創業を希望していた人物を紹介され、事業を引継ぎ、自らは従業員として新経営者を支えているケース。
事例3:債務超過でも事業譲渡が可能
大幅な債務超過だったが、M&A専門家に相談したところ、販路や知名度を評価するスポンサーが現れ、全事業を譲渡し、自身は新たな事業の立ち上げに取り組んでいるケース。
事例4:後継者不在の中での全員継続雇用の実現
後継者不在だったが、熟練職人の技術力と加工技術によるシナジー効果を見込んだ買い手側企業により、譲渡額を譲歩することで、第一条件であった従業員全員の継続雇用を実現したケース。
これらの事例から、M&A成功のための要因として以下の点が挙げられます。
条件が悪くても自ら可能性を閉ざさず、公的機関やM&A専門業者に相談したこと。
自社に何らかの強みがあり、それが買い手側企業に評価されたこと。
全ての希望条件は受け入れられない前提で、妥協できることころは妥協したこと。
これらの要因が、円滑な事業売却やM&Aの成功に繋がると考えられます。
失敗事例から学ぶこと
「中小M&Aガイドライン」には、事業売却を含む多数の中小M&A失敗事例も掲載されています。ここからいくつかの具体的なケースをピックアップし、失敗した要因について分析します。
事例1:M&Aの検討が遅れた結果、資金繰りが尽きる
業績の悪化に伴いM&Aを検討するに至り、いくつかの候補先が出てきたものの、検討開始が遅れた結果、候補先が決断する前に資金繰りが尽きてしまい、結局廃業に至ったケース。
事例2:情報開示の誤りが交渉破綻を招いた
M&A専門機関からの紹介で売却先が見つかり順調に交渉を進めていたが、事前取り決めに反して売り手側社長が最終契約前に関係者へ情報開示をしたため、交渉が破綻したケース。
事例3:社内合意がない状態での交渉進行
買い手側企業との事業譲渡の交渉を進めていたが、社内の合意が取れておらず、M&Aに反対する他経営陣との間で内紛が起こり、交渉が打ち切りとなったケース。
事例4:不誠実な態度が交渉決裂を招いた
順調に交渉が進んで基本合意まで至っていたが、売り手側社長が十分な情報開示を行わず、契約条件確定後に過大な要求を提示するなどの不誠実な態度を取った結果、買い手側企業の信頼を損ない、交渉が決裂となったケース。
これらの失敗事例から、M&A失敗の要因として以下の点が考察されます。
M&Aの検討に着手したタイミングが遅すぎたこと。
情報漏洩に対する配慮を怠ったこと。
社内の合意がない状態で交渉を進めたこと。
相手企業に対して不誠実な態度をとったこと。
これらの失敗要因を踏まえ、M&Aを検討する際には十分な注意が必要です。
適切な事業売却のための戦略と心構え
事業売却の成功事例と失敗事例を見てきましたが、これらのケースから導かれる、適切な事業売却のための戦略と心構えについて、以下にまとめます。
事業売却によるM&Aに関心を持つ経営者の方々は、これらのポイントに留意しながら検討されることをお勧めします。
-
早い段階から検討に着手し、適切なタイミングで専門機関に相談する
-
日常の事業活動を通して自社の強みを磨き上げ、交渉の場では効果的にアピールする
-
社内経営層の間では事前に合意形成をしておき、十分なコミュニケーションをとる
-
希望条件には優先順位をつけ、妥協ラインを明確にしたうえで交渉に臨む
-
手続き全般に渡って守秘義務を遵守し関係者への情報漏洩を防ぐ
-
相手側企業には最後まで誠実な態度をとり、成約後も協力する姿勢を保持する
事業承継を相談するなら日本提携支援におまかせ
中小M&Aでは一般的な手法となる事業売却について、その特徴や進め方のポイントを解説してきました。
事業売却を含む事業承継には専門知識も必要になり一定の時間がかかるため、早い段階から専門家の支援を仰ぎ、計画的に進めることが重要になります。
日本提携支援には豊富な実績、経験のある専門家が多数在籍していますので、事業承継に関する専門家の活用方法や留意点について具体的なアドバイスが可能です。
当社では相談者の方から手数料をいただいておりませんので費用面でも安心してご相談いただけます。お気軽にお問合せください。