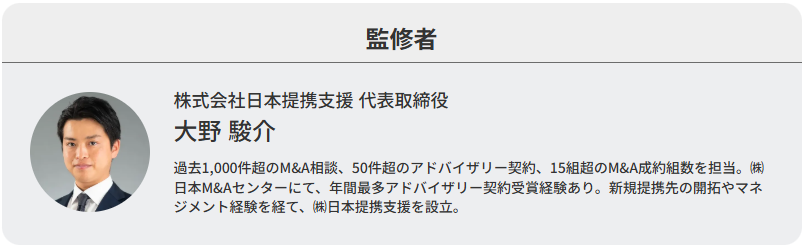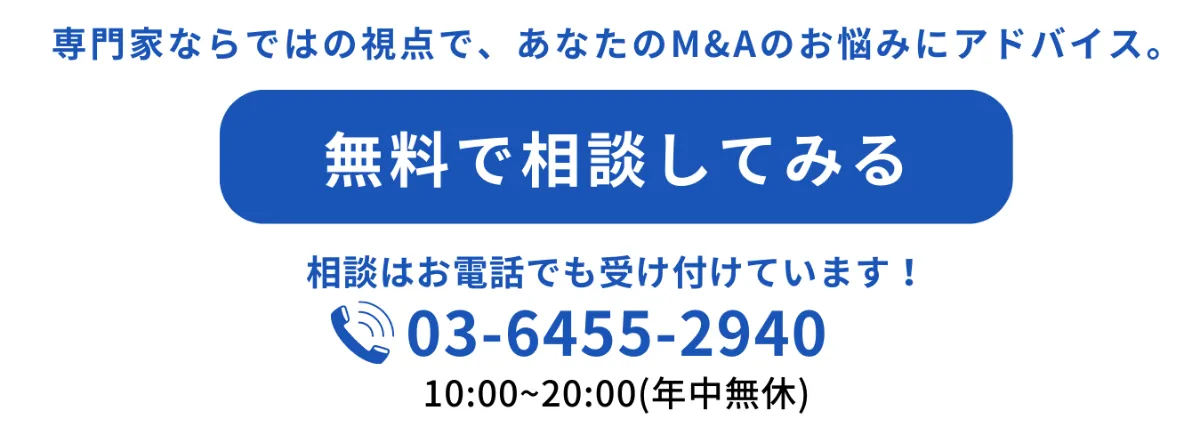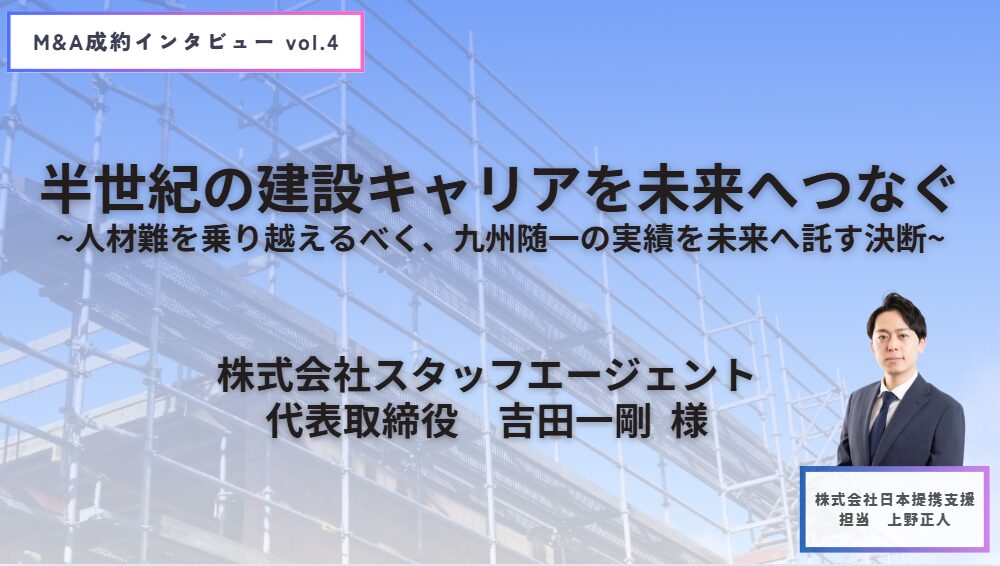高齢化社会を迎えるわが国にとって、経営者の高齢化も問題になっています。
経営者高齢化・後継者不足が叫ばれる昨今において、事業承継を円滑に進めることは重要なテーマですが、ほとんどの経営者にとって事業承継とは未経験の領域といっても過言ではありません。
そんな中、注目されているのが事業承継分野でのコンサルタントです。
事業承継コンサルは特定の資格保有者が独占して提供するサービスではなく、弁護士、会計士、税理士、経営コンサルタントなど、様々な職種の専門家が参入している業界です。
本コラムでは事業承継コンサルタントの選び方、依頼する場合のメリット・デメリットなどを詳しく解説していきます。
事業承継にはどんな種類があるのか
一言で「事業承継」といっても、様々な方法が存在します。事業承継の方法は主に3つの類型に分けることができます。
-
親族内承継
-
従業員承継
-
第三者承継
(1)親族内承継
現経営者の親族が承継するパターンです。
親戚が後継者となるケースも存在しますが、多くの場合、経営者の子どもが承継することがほとんどです。
日本では古くから「親の会社は子どもが継ぐもの」という文化が根付いているため、親族内承継は社内的にも対外的にも理解の得られやすい事業承継の方法といえます。
一方で、多様な人生の選択肢が存在する現在では、子どもに親の会社を継ぐ意思がないパターンも多く存在します。
また、中には子どもに自分の会社を継がせたくないと考える経営者も一定数存在します。
子どもに自社を継がせたいと考えるのであれば、親子間で会社の将来について話し合う機会を持ちにくい場合もありますが、子どもが会社を引き継ぐ意思があることを必ず確認しておく必要があります。
(2)従業員承継
親族内に後継者候補がいない場合に選択されやすいのが従業員承継です。
社内の信頼のおける従業員や役員に会社を引き継ぐことを指します。
後継者として選ばれる従業員・役員は社歴も長く、会社の文化・風土、事業内容に精通していることが多いため、従業員承継は社内外から理解されやすい事業承継の方法であることがメリットです。
一方で、後継者候補の従業員・役員が会社を引き継ぐ(購入する)だけの資金を持ち合わせていないケースが多いなど、後継者の金銭的な負担が重い場合がある点がデメリットといえます。
(3)第三者承継
会社を第三者が引き継ぐ、いわゆるM&Aで事業承継するパターンです。
一昔前までM&Aは買収側を「ハゲタカ」に例えるなど、あまり良い印象を持たれていなかった影響か、親族内・従業員に後継者がいない場合の最終選択肢として認識されていました。
しかし、経営者高齢化・後継者不足が深刻な状況である現在において、M&Aは後継者不足による廃業を打開する有効な手段として認識されるようになってきました。
買い手が経営者であることが多く、売り手にとっては後継者を経営者として育成する必要がない、というメリットがあります。
また、経営者(=株主)が会社売却の対価を現金で得られる点もメリットでしょう。
一方で、手続きが煩雑でわかりにくい、仲介業者に支払う手数料が高い、といったデメリットも存在します。
コンサルタントが提供するサービス
様々なコンサルタントが様々なサービスを提供していますが、提供されるサービスは大きく分けて以下の4つにまとめることができます。
-
事業承継プランの策定・実行支援
-
後継者育成支援
-
会社資産の承継対策
-
M&Aの実行支援
(1)事業承継プランの策定・実行支援
自社のこれまで、および現状を多面的に分析し、今後の事業承継においてどのような道筋をたどるのが最適なのか、ロードマップを描きます。
当然、経営者の事業承継における意向が優先(多くは親族内承継)されますが、現状分析の結果によっては、他の選択肢が提案されることもあります。
事業承継プランを明確にする作業のなかで、親族内承継しか選択肢として考えていなかった経営者がM&Aを選択する可能性を見出すケースも多くみられます。
また、事業承継プラン策定だけに留まらず、実際の事業承継に向けて伴走型でサポートするコンサルタントも存在します。
(2)後継者育成支援
後継者の育成は事業承継において、もっとも長期的な視点が必要となる課題です。
事実、中小企業庁発行の中小企業白書(2014年版)においても、経営者の多くが後継者の育成には5~10年のスパンが必要であると回答しています。
引用元:中小企業白書(2014年版)
後継者育成支援を行う事業承継コンサルタントは、後継者候補の育成プランの策定・提案などを行い、今後どのように後継者を育てるか、という観点で支援します。
(3)会社資産の承継対策
会社資産の譲渡
会社の資産(特に現預金、土地、建物など)を後継者に承継する際、譲渡資金の調達や贈与税・相続税の問題は避けて通れません。
私的な資産と異なり、法人の資産は非常に高額となるケースも多く、例え会社の業績が悪くても保有する不動産の評価額が高い場合など、譲渡金額、贈与税・相続税は個人では負担できないほど高額になることもあります。
資産の承継対策無しに事業承継を行うことは得策でなく、税務面であれば事前に顧問の会計士・税理士に相談する経営者がほとんどでしょう。
株式(経営権)の譲渡対策
法人であれば株式の譲渡を通して会社の資産や経営権を後継者に譲渡することになりますが、後継者が事業承継後、安定的に経営を行うためには後継者に大半の株式を集中させる必要があります。
対策無しに株式譲渡を行う場合、親族から異論が出るケースもあり(俗にいう争族)、弁護士等の専門家を交え、事前に対策を施す必要もあります。
(4)M&Aの実行支援
自社をM&Aによって第三者承継する場合、以下の観点も含め多面的に検討する必要があります。
-
いつまでに売却するのか
-
自社の評価額はいくらか、いくらで売却するのか
-
どのような手段で売却するのか
-
従業員の処遇はどうするのか
-
どのタイミングで社内に周知するのか
-
誰に、どのように買収を持ちかけるのか
-
どのような契約書を準備する必要があるのか
-
買収候補者とはどのように交渉を進めるのか
-
M&A成立後の手続きはどのようなものがあるのか
M&Aの実行支援を行うコンサルタントはM&Aに関わるすべてのプロセスにおいて専門的なアドバイスを行います。
買い手候補企業の選定、候補企業へのアプローチ、M&A交渉も一任することが可能です。
事業承継コンサルタントの選び方
事業承継のコンサルサービスを提供する専門家は多種多様であるため、どのような専門家にコンサルを依頼するかは難しい点です。
ここでは、事業承継コンサルを選ぶ際に参考となるポイントについて解説していきます。
-
実績と経験
-
専門分野とのマッチング
-
コミュニケーションスキル
(1)実績と経験
コンサルタントが今まで培ってきた実績と経験が、コンサルの力量に直結するといっても過言ではありません。
事業承継を行う上で想定外のトラブルが発生することは常ですが、コンサルタントが多くの経験を積んでいれば、適宜柔軟なアドバイスを受けることが期待できます。
事業承継コンサルタントが今までどんな事業承継に携わってきたか、事前に確認しておくことが重要です。
また、実績・経験が豊富なコンサルタントであれば、専門家ネットワークを多く保有している可能性が高いです。たとえ、そのコンサルタントが単独では対応しきれない事案が発生しても、外部のネットワークを活用し、課題解決に導くことも可能です。
(2)専門分野とのマッチング
コンサルタントによって対応できる業務範囲が異なります。
税金関係であれば、会計士・税理士、相続関係であれば弁護士、といったようにコンサルを依頼する内容によって相談先が変わります。
さらに、製造業に強い、サービス業に強いなど、特定の業種・業態に特化したコンサルを提供している事業承継コンサルタントも存在します。
自社の現状や課題に応じて、どんなコンサルが必要なのか検討することも事業承継コンサルタントを選ぶポイントです。
(3)コミュニケーションスキル
コンサルタントのコミュニケーションスキルも重要なポイントです。
コミュニケーションスキルはコンサルタントとの「相性」とも言い換えることができるでしょう。
コンサルは経営者とコンサルタントの対話を通して初めて成立するサービスである以上、人同士の相性は切り離すことができません。
人は感情で動く側面も大きく、正論だけでは解決しない課題も存在します。
「言っていることは正しいのだけど…」と腑に落ちない場面もあるかもしれません。
事業承継というセンシティブな最重要課題を共に乗り越えるためのパートナーとして、そのコンサルタントが信頼のおける人物か否かを見極める必要があります。
事業承継コンサルタント活用のメリット
ここまで、事象承継のコンサルタントのサポート内容について詳細に述べてきましたが、実際にコンサルタントを活用することのメリットについて説明します。
スムーズな事業承継の実現
事業承継コンサルタントを活用する最大のメリットは最短ルートでの事業承継の実現が期待できることでしょう。
事業承継コンサルタントは事業承継の経験や実績、知識が豊富であるため、事業承継でつまずきやすいポイント、失敗事例も数多く把握しています。
そういった知見を活かし、事業承継の障害になり得る要素を事前に取り除く対策が講じられることは大きなメリットです。
事業承継計画の策定
自社の現状分析を行ったうえで事業承継計画を策定する事業承継コンサルタントも多く存在します。
事業承継計画を策定するメリットは以下3点です。
-
事業承継に向けた道筋を見える化することで自社の現在地を把握することができる
-
事業承継に必要な作業、手続き、準備を明確にすることができる
-
事業承継計画の存在を対外的にアピールすることで社外からの信頼を獲得できる
特に、高齢の経営者であれば、取引先や得意先から事業承継について心配されていることも少なくありません。
しっかりとした事業承継計画が存在することは対外的にも安心材料として認識され、継続取引に貢献することが期待できます。
経営者・オーナーの負担軽減
複数回の事業承継を経験している経営者は稀ではないでしょうか。
ほとんどの経営者にとって事業承継は初めてのイベントであるため、経営者単独で行う場合、手探りで進めることとなります。
自社経営と事業承継を同時並行で行うことになり、経営者にかかる負担は相当なものとなります。
事業承継コンサルタントに事業承継計画の策定、考えられるリスクやその回避策の提案などを依頼できれば、経営者の負担は一定程度軽減できるでしょう。
事業承継コンサルタントの料金体系
基本料金と成果報酬
料金体系は依頼するコンサル内容によって様々です。
おおよそ10万円~30万円が相場といわれていますが、A社で含まれているサービスをB社ではオプションとして提供しているなど、会社によって契約内容は変わります。
スポット契約か顧問契約(長期契約)か、着手金が発生するのか否か等も検討するポイントです。
着手金はおおむね10万円~20万円が相場です。
M&Aによる事業承継を行う場合で、M&A専門会社にコンサルを依頼するのであれば、別途M&A成功報酬などが発生します。
|
業務内容 |
契約 |
料金相場 |
|
事業承継計画の策定 |
スポット |
20万円~300万円 |
|
事業承継の伴走支援 |
顧問 |
10万円~20万円/月 |
|
自社株の評価 |
スポット |
10万円~30万円 |
|
相続税申告 |
スポット |
相続財産の約1% |
|
相続登記 |
スポット |
5万円~10万円 |
予算と費用対効果の検討
事業承継コンサルタントを起用する場合、当然手数料が発生します。
支払う手数料以上のメリットを享受できるのか、という費用対効果は十分に検討を行いましょう。
コンサルタントは専門的な知識、ノウハウを活用することで円滑な事業承継支援を行います。
以下の観点から、事業承継コンサルタントを活用するか否かを検討しましょう。
-
自社にどれだけ事業承継に関するノウハウがあるのか
-
事業承継対策を行うための、時間的・人員的なリソースは確保できるか
-
事業承継に関わる費用をどれだけ捻出できるのか
事業承継コンサルタントとの契約のポイント
自社のニーズに合わせた選択を行うこと
自社のニーズ、現状に合った事業承継コンサルタントと契約をする必要があります。
例えば、自社株式の評価額を知りたいのであれば、税理士にスポットコンサルを依頼するなど、適切なコンサルタント・契約を選択しましょう。
事業承継コンサルタントと契約を結ぶ際、コンサルタントと打合せを行い、自社が希望すること、コンサルタントが提供できるサービスをしっかり確認します。
事業承継コンサルタントが提出する成果物についても確認しておきましょう。
口頭でのコンサル以外に、事業承継計画書や株価算定報告書といった、目に見える成果物の提出があるかどうかも事前に確認しておくポイントです。
契約後にお互いの認識に齟齬が出ないよう、事前の入念な打合せが重要となります。
過度な期待を持たないこと
コンサルタントは万能ではありません。
事業承継コンサルタントにコンサルティングを依頼したからといって、現状が劇的に改善することは稀であり、過度の期待は禁物です。
事業承継コンサルタントは事業承継の道筋の提案、想定リスク回避対策の提案などを行いますが、提案を実行するのは経営者自身であり、コンサルタントではありません。
事業承継を行ううえで、事業承継をやり切る覚悟と責任は経営者に委ねられていることも事実です。
また、上の図は事業承継の一選択肢であるM&Aの各段階において、関連する事業承継コンサルタント(主な支援機関)を示したものですが、M&Aだけでもこれだけ多くのコンサルタントが存在します。
これは、単独の事業承継コンサルタントでは、事業承継のすべての局面をカバーできないことを表しているともいえるでしょう。
加えて、M&Aのフェーズごとに専門性を持つ支援パートナーが存在します。
これは、単独の事業承継コンサルタントでは、事業承継のすべての局面をカバーできないことを表しているともいえるでしょう。
依頼した事業承継コンサルタントの対応可能な業務範囲を把握しておくことも重要です。
継続的なコミュニケーションを確保すること
事業承継を進めるにうえで、想定外の事案が発生することもよくあります。
トラブルが起こったときや不安に思うことを事業承継コンサルタントにすぐに相談できる体制を整えておきましょう。
コンサルは経営者との対話をベースに成立するものなので、コンサルタントとの継続的なコミュニケーション確保は必須です。
なお、コンサル契約によっては、コンサルタントの訪問頻度、訪問時以外の相談方法(手段)など、コミュニケーション方法や回数について定められている場合もありますので、契約内容を入念に確認しましょう。
事業承継についてお困りなら日本提携支援に相談
事業承継のコンサルタントについて解説してきました。
事業承継は長期的な視点が必要であるうえ、検討すべき事案も多数存在します。
そのため、事業承継コンサルタントを活用することは円滑に事業承継を進めるために有効な手段と考えられます。
しかしながら、事業承継コンサルタントは数多く存在し、各コンサルタントの対応可能業務、得意分野、提供サービスは多岐に渡るため、何を基準に誰に依頼するかの判断は難しい点です。
事業承継コンサルタントをお探しの場合は是非当社にご相談ください。
日本提携支援には豊富な実績、経験のある専門家が多数在籍していますので、事業継続に向けたアドバイスが可能です。
当社では相談者の方から手数料をいただいておりませんので費用面でも安心してご相談いただけます。お気軽にお問合せください。