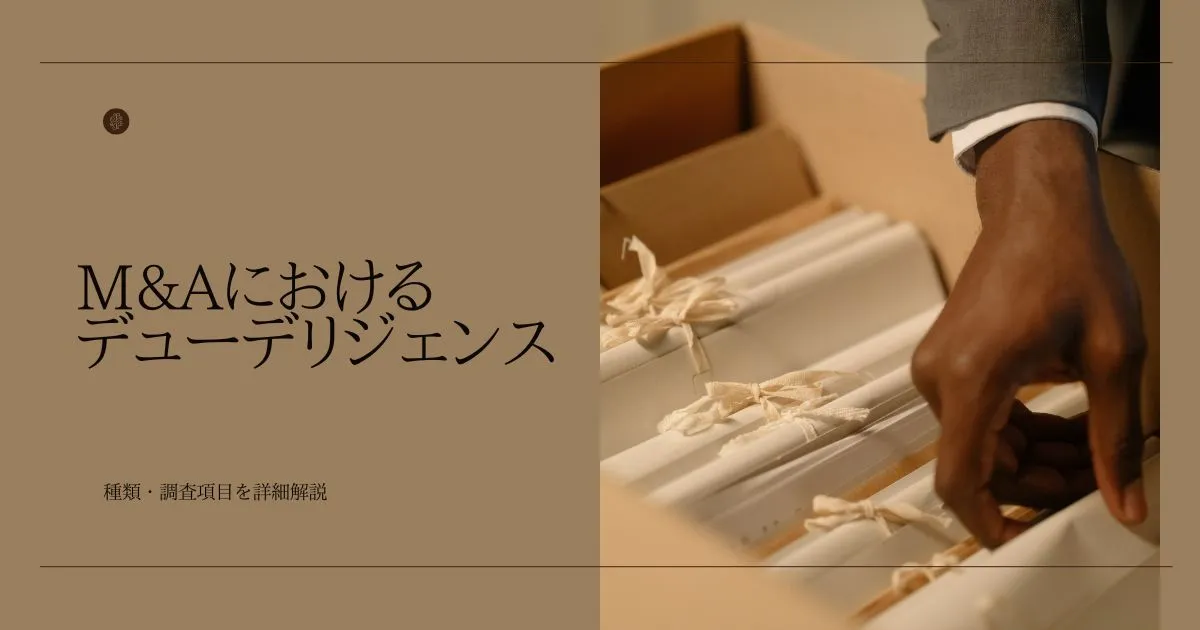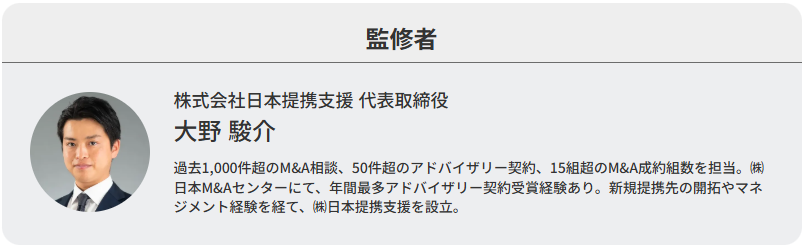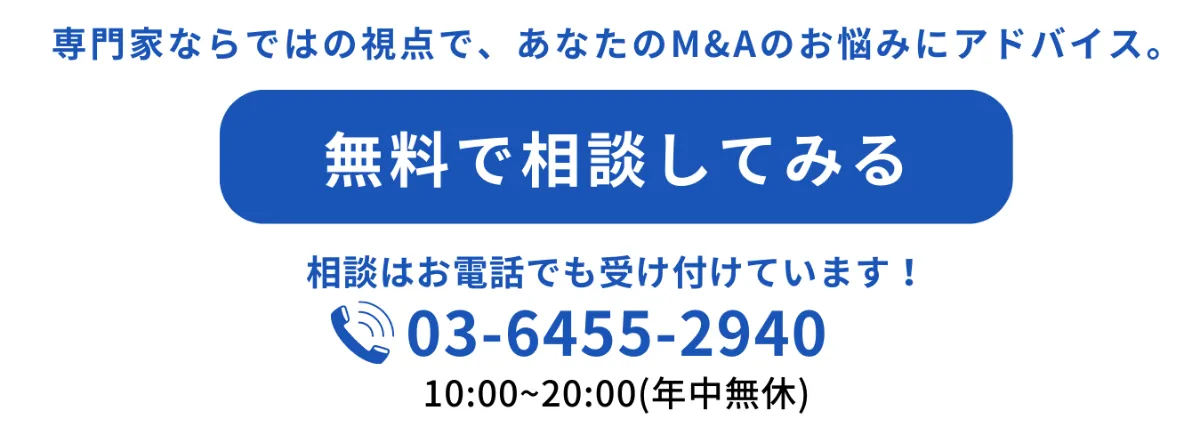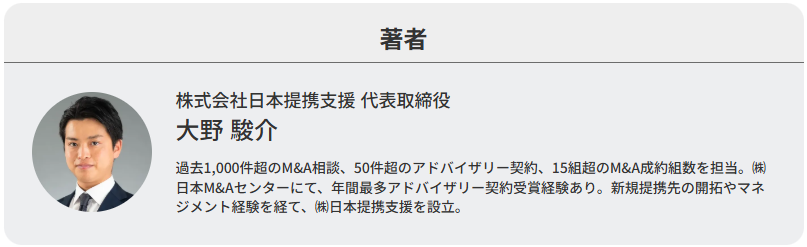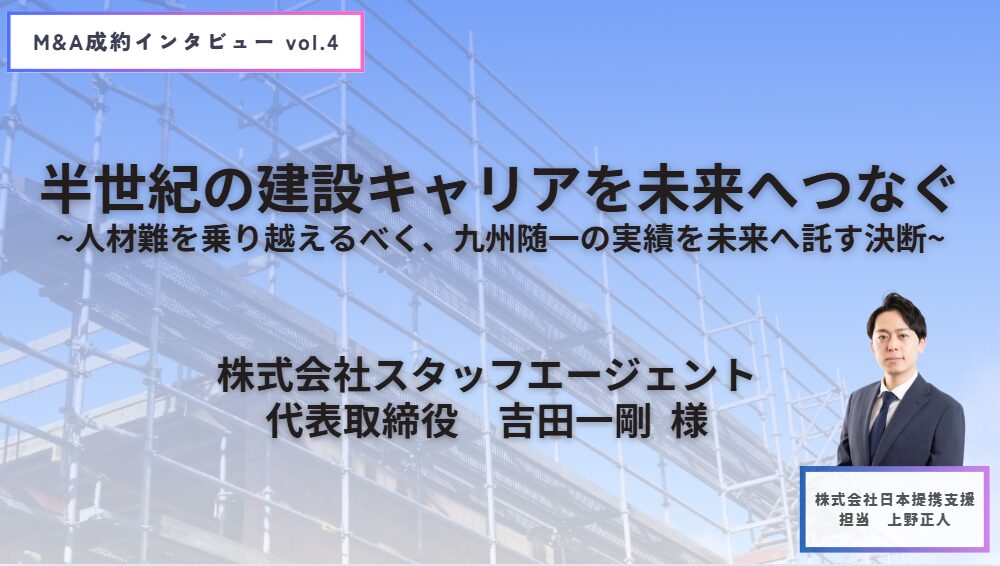昨今では中堅中小企業でもM&Aが浸透してきたことにより、デューデリジェンス(DD)という言葉を聞いたことがある経営者も多くなってきたと思います。
M&Aを経験した経営者にはDDが大変だったという感想を話す人も多いと思います。
確かに中堅中小企業のM&AではDDは一社の買い手企業によって相対で行われることが多く、制限なく様々な事項を買い手企業や専門家に確認されるためデューデリジェンスは大変な側面があります。
この記事では中堅中小企業のM&Aで中心になる相対取引を前提にM&Aでの自社の譲渡を検討する経営者にとって不安に感じるDDを解説します。
デューデリジェンス(DD)とは
デューデリジェンスの定義と目的
デューデリジェンス(DD)とはM&Aのプロセスの中で買い手企業が対象会社の財務・法務・税務・ビジネス・環境・ITの観点から様々な事項を分析し、検討するものです。
中堅中小企業のM&Aでは売り手がオーナー経営者として対象会社について熟知している一方で買い手企業は対象会社の情報の入手が限定されることが多く情報の非対称性が存在します。
そこで買い手企業は外部の専門家(公認会計士、弁護士、税理士、コンサルティング会社など)を雇って対象会社の事業の潜在的な問題やリスク、収益性や今後の事業の見通しなどを分析しM&Aの検討に役立てます。
デューデリジェンスのプロセス
DDは主に以下の3つのプロセスに分かれます。
①初期資料開示
②Q&Aの実施
③マネジメントインタビュ
①初期資料開示
初期資料開示は、専門家がM&Aを検討するために作った資料依頼リストに基づいて対象会社に資料開示を求めることです
資料依頼リストは主にMicrosoft Excelを用いて作成されます。
DDは実施する期間が限られていることもあり、専門家にとって確認したい資料の優先度があるため優先度の順位付け(高、中、低など)をされることが多いです。
また、専門家は対象会社に関して限られた情報を基に資料依頼リストを作成するため、対象会社に幅広い資料の開示を依頼します。
このため売り手は、資料依頼リストの中で対象会社に存在しない事項に対する資料や作成していない資料に対しては「該当事実無」や「作成無」などExcelシートにコメントすることでDDを円滑に進めることができます。
資料依頼リストは欧米ではIRL(Information Request List)と呼ばれており、日本のDDプロセスでもIRLと呼ばれることがあります。
②Q&A
資料依頼リストに基づいての資料開示が進んでくるとQ&Aのプロセスに移ります。
Q&Aのプロセスは、専門家が初期資料を見る中で疑問に思ったことや追加で確認したい資料に関してExcelシートにリスト化して対象会社に確認を求めることで進める形式が大半です。
Q&Aリストは資料依頼リスト同様に優先的に確認したい事項の順に優先度の順位付け(高、中、低など)することが多いです。
Q&Aリストにおいては初期資料や先に確認した質問に対して質問することが多いのでどの資料を基に質問をしているかを明示するために参照資料のファイル名(「決算書202103期.pdf」、「財務Q&ANo4」など)を記載して進めることが多いです。
③マネジメントインタビュー
マネジメントインタビューは買い手企業や専門家が対象会社の経営陣やキーパーソンに当たる従業員などへ行う個別のインタビューです。
資料依頼リストで開示された資料やQ&Aリストでの回答は書類や帳簿などの文字媒体であり、定性的な情報は読み取りにくいです。
そこでマネジメントインタビューを行うことで文字媒体だけでは読み取りにくい経営陣の経営への考え方やリーダーシップ、会社の管理体制、今後の事業に対する見通しを確認することができます。
デューデリジェンスとM&Aの関係性
DDは対象会社の事業の潜在的な問題点やリスク、収益性を分析するプロセスです。
このため買い手企業はDDをM&Aの最終的な譲渡対価などの経済的条件の検討や最終契約書の交渉に用います。
デューデリジェンスの種類
財務デューデリジェンス(FDD)
財務デューデリジェンスは、対象会社の財務上の詳細な分析・調査をするもので収益性や安全性を確認する手続きです。
中堅中小企業のM&Aでは通常直近3~5年の会計期間を調査することが大半です。
財務デューデリジェンスは主に買い手企業が雇った公認会計士が行います。
財務デューデリジェンスで分析される事項は以下の5点が挙げられます。
・正常収益力と調整項目
・実態純資産分析
・運転資本分析(回転日数、季節性など)
・コスト構造分析
・設備投資・減価償却分析
正常収益力と調整項目
正常収益力とは買い手企業が対象会社を譲り受けた際に、対象会社が継続的に稼げる利益のことを言います。
正常収益力は主に償却前営業利益(EBITDA、営業利益+減価償却費)を用います。
過去の収益と正常収益力との差異の調整は主に以下の2点を行います。
①計画期間との差異の調整
②一過性費用の調整
①計画期間との差異の調整
計画期間との差異の調整買い手企業が対象会社を譲り受けた後に不要になる費用を控除する調整です。
中堅中小企業はオーナー経営者によって経営されていることが多く、オーナー関連費用(過大な役員報酬・接待交際費など)の調整が多く見られます。
M&Aに伴ってオーナー経営者が引退する場合にはオーナー関連費用が無くなるため正常収益力にはオーナー関連費用を加算します。
②一過性の収益・費用の調整
通常の事業運営で発生しない特定の収益や費用を一過性の収益・費用と呼びます。これらはある会計年度だけで発生し、継続的には生じません。
・一過性の収益
一過性の収益は、特定の取引から生じた収益のことを言います。これは通常期には発生しないものであり、継続的に発生するものではありません。
・一過性の費用
一過性の費用とは、通常期には発生しない特定の費用のことを指します。創業何周年の記念旅行に伴う福利厚生費や、一部事業の撤退に伴う費用などが例として挙げられます。
・一過性の収益の扱い
一過性の収益は、今後継続的に発生しない収益です。そのため、企業の正常な収益力を算出する際には、利益からこれを除く必要があります。
・一過性の費用の扱い
一方、一過性の費用は、通常は発生しない費用です。従って、企業の正常な収益力を算出する際には、これを利益に加える必要があります。
法務デューデリジェンス(LDD)
法務デューデリジェンスは、M&Aを実施する上での法務的なリスクを分析する手続きです。
法務デューデリジェンスは主に買い手企業が雇った弁護士が行います。
法務デューデリジェンスでは主に以下の6点の事項が調査されます。
・組織・株式の変遷
・契約
・資産・負債
・許認可・知的財産・コンプライアンス
・人事・労務
・訴訟・係争
・環境問題
法務デューデリジェンスでは、対象会社が議事録や契約書などの書類をデータで提供するため対象会社の事務的な負担がやや大きくなることが多いです。
税務デューデリジェンス(TDD)
税務デューデリジェンスは税務上のリスクに関して分析する手続きです。
税務デューデリジェンスは主に買い手企業が雇った税理士が行います。
買い手企業が財務デューデリジェンスと税務デューデリジェンスを別のアドバイザーに依頼することは少なく、同じ会計事務所が財務デューデリジェンスと税務デューデリジェンスを一括して委託されることが大半です。
税務デューデリジェンスでは主に税務上のリスク (過去の税務調査の状況の確認など)や繰越欠損金の有無などを分析します。
事業デューデリジェンス(BDD)
事業デューデリジェンスは対象会社の事業についての分析手続きで、将来計画を具体化するために実施されます。これを行う主体は買い手企業の役職員であることもあり、また、外部のコンサルティング会社がこれを担当することもあります。
市場環境の分析
事業デューデリジェンスでは、対象会社の事業が展開される市場環境を分析します。これにはマクロ環境や競合分析が含まれます。
事業の強みと課題の分析
また、対象会社の運営面から見て、事業上の強みと課題を洗い出します。
事業デューデリジェンスと他のデューデリジェンスの違い
財務デューデリジェンスや法務デューデリジェンス、税務デューデリジェンスでは、対象会社にM&A取引を中止するような致命的な問題がないかを確認します。
しかし、事業デューデリジェンスでは、致命的な問題が見つかることは比較的少ないです。
事業デューデリジェンスで発見される課題
事業デューデリジェンスでは、多くの事業上の課題が発見されますが、これらは経営戦略上の課題であることが多く、取引価格に反映させる検討点として用いたり、買い手企業が今後の事業運営の戦略をどう立てるかという議論の材料となります。
事業デューデリジェンスの役割
事業デューデリジェンスでは、対象会社から開示された情報を基に対象会社の事業計画の可能性を分析し、今後の事業戦略を策定します。
環境デューデリジェンス(EDD)
環境デューデリジェンスは対象会社の用地の環境面のリスク(土壌汚染や廃棄排水、適法性など)を分析する作業です。
対象会社が工場を有していた際に行われることが多いです。
近年はESGを意識した経営を求められることが多く、環境デューデリジェンスがより注目される傾向にあります。
ITデューデリジェンス
ITデューデリジェンスは対象会社のシステムに関する状況を分析し、M&Aにあたってどのような課題があってどのように対応していくかを分析する手続きです。
買い手企業が対象会社を譲り受ける上でシステムの統合が行えるか、対象会社が保有するデータをスムーズに移行できるかを分析する手続きであり、M&A後の統合を意識したDDです。
デューデリジェンスの進め方
デューデリジェンス計画の策定
デューデリジェンスの計画を綿密に策定することがデューデリジェンスを円滑に進めるためには重要です。
デューデリジェンスは、主に以下の手順で進められます。
①初期資料開示
②Q&Aの実施
③マネジメントインタビュー
デューデリジェンス計画を立てる上では売り手や対象会社と綿密にコミュニケーションを取り、いつまでに初期資料の重要な資料の開示を終える、マネジメントインタビューまでに2週間ほどQ&Aリストのやり取りをするなどスケジュールに落とし込むことが必要です。
デューデリジェンスのスケジュールをガントチャートのような形式で売り手や買い手が合意して進めることは、スケジュールが順調に進んでいるか、何がボトルネックとなって進行が遅れているかなど当事者同士の認識を揃えることができるためお勧めする進行方法です。
データルームの活用方法
最近のデューデリジェンスでは、クラウドシステム上の「バーチャルデータルーム(VDR)」に開示資料を格納することが主流となっています。これは15年以上前のM&A取引とは異なります。
当時、IT技術はまだ発展途上であり、紙の資料を会議室などで開示していました。このような会議室のことをデータルームと呼んでいました。
VDRの特徴と活用方法
現在では、セキュリティが確保されたVDRに、買い手企業の役職員や外部の専門家にアクセス権を付与し、資料を開示します。
Q&Aプロセスの効率化
VDRを使うと、Q&Aリストで質問する際、どのフォルダのどの資料に対する質問を行っているのかを明確に示すことができます。これにより、Q&Aプロセスを円滑に進行することができます。
情報の保護
また、特定の情報(取締役会議事録の具体的な記載など)や従業員の個人情報など、買い手企業に知られたくない情報については、VDRのマスキング機能(塗りつぶし機能)を使って隠すことが可能です。
これにより、情報漏洩のリスクを軽減することができます。
専門家との連携方法
買い手企業にとって専門家との連携がデューデリジェンスの成功には必要不可欠です。
M&Aに慣れていない買い手企業の場合、専門家にデューデリジェンス・プロセスを任せきりにして報告書を受け取るだけという進行をする場合がありますが、失敗に陥る場合が多いです。
デューデリジェンスに入る前に対象会社における懸念事項を事前に伝えておき、懸念事項に関するQ&Aについてはデューデリジェンスの進行中に目を通すことで論点の把握がスムーズにできます。
また、専門家によっては、売り手に対して専門用語を駆使して質問した際に質問される側の売り手が質問の意味がわからず戸惑うことが見受けられます。
こうした場合は、専門家を雇っている側の買い手企業が適宜補足を加えることや、わかりやすく説明する様に専門家に依頼するなど間に入ることも重要です。
デューデリジェンス報告書の解読法
デューデリジェンス報告書は多い場合100ページを超える分量になることがあり、M&A取引の中で全部を読み解くことはM&A取引に手慣れていないと難しいです。
お勧めする解読法は以下の2点の手順です。
①取引を停止する事項はないか
②発見された事項を取引価格や最終契約書にどのように反映するべきか
①取引を停止する事項はないか
デューデリジェンス報告書の冒頭に取引を停止するべき事項の有無が記載されます。
実際の案件での事例を挙げると許認可を維持する上で法令違反状態であり、監督官庁に知られると許認可が取り消しになる事項が発見されたことがありました。
②発見された事項を取引価格や最終契約書にどのように反映するべきか
優れたデューデリジェンス報告書はデューデリジェンスでの検出事項を最終契約の交渉にどのように反映させるべきかが記載されております。
例えば対象会社に未払残業代が3年間で10百万円あることがデューデリジェンスの中で判明した事例があったとします。
この場合、デューデリジェンス報告書に株式譲渡契約書の特別補償条項に記載し、実際に未払残業代を支払うように記載されていると検出された問題点をどのように対処するべきかわかります。
デューデリジェンスでの注意点
デューデリジェンス中のリスク管理
M&Aは秘密保持に始まり、秘密保持に終わると言われております。
デューデリジェンスは対象会社の大量の情報を買い手企業に開示するため対象会社の従業員にM&Aを検討していることを知られる可能性があります。
M&Aを秘密裏に行うためにM&A案件のことをPJネーム(コードネーム)で呼ぶことや対象会社の拠点訪問を従業員の休日に設定したりする工夫は重要です。
デューデリジェンスの期間とコスト
デューデリジェンスの期間は大体1~3か月程度が一般的です。
コストは、雇う専門家の人数やデューデリジェンスの確認範囲に拠りますが、取引金額が5億円以下の中堅中小企業のM&Aの場合、財務・税務DDが200〜500万円程度、法務DDが300〜700万円程度、事業DDが500~1,000万円程度の範囲に収まることが多いです。
金額に関しては複数の専門家に声掛けし、相見積もりを取得することで一定の公平な金額を確認できます。
特に法務デューデリジェンスは、弁護士が動いた時間に対して請求されるタイムチャージ制度が取られることが多いです。
タイムチャージ制度が取られる場合は上限を設けることが検討可能なのかなどを確認することが有益です。
デューデリジェンスの結果の活用法
デューデリジェンスの結果は最終契約の交渉に活用します。
取引価格に減額する事項か、何か問題が発生したときに売り手に補償してもらう事項なのかなど検討します。
例えば労務関係の法令違反状態があった場合に取引実行の前に治癒するように依頼するべき事項か、取引実行後に共に解決する必要がある事項かなどデューデリジェンス報告書を読みながら専門家と議論していきます。
デューデリジェンスと情報漏洩の防止策
デューデリジェンス期間は対象会社の情報収集をすることや買い手企業や専門家が対象会社に訪問するなど情報漏洩が起こりやすいです。
例えば専門家が対象会社を訪問する際には、会社を良くするためにコンサルティングを依頼しているなどデューデリジェンスとは別の用件で伝えるなどが考えられます。
デューデリジェンスの具体的な調査項目
会社全体の調査項目(事業デューデリジェンス)
事業デューデリジェンスの調査項目としては、以下の3点が挙げられます。
・市場分析
・業界構造分析
・競争力分析
財務・法務・税務の調査項目
財務デューデリジェンスの調査項目は以下の5点が挙げられます。
・正常収益力と調整項目
・実態純資産分析
・運転資本分析(回転日数、季節性など)
・コスト構造分析
・設備投資・減価償却分析
法務デューデリジェンスの調査項目は以下の7点が挙げられます。
・組織・株式の変遷
・契約
・資産・負債
・許認可・知的財産・コンプライアンス
・人事・労務
・訴訟・係争
・環境問題
税務デューデリジェンスの調査項目は以下の3点が挙げられます。
・税務コンプライアンスの確認
・過去の税務調査の状況確認
・繰越欠損金の有無の確認
環境の調査項目
環境デューデリジェンスは対象会社が製造業のときに主に行われます。
調査項目は、対象会社の工場に土壌汚染がないか、建物にアスベストが使用されていないかなどが確認されます。
IT・知的財産の調査項目
ITデューデリジェンスは主にM&A後のデータ移管やシステム統合の可否を確認されます。
最近では対象会社の持つデータの資産性がどの程度かを定量的に算出するIT DDも行われています。
知的財産デューデリジェンスは法務デューデリジェンスのスコープに含まれることが多く、対象会社の知的財産が適切に保護されているかを調査します。
デューデリジェンスの効果的な活用法
M&A成功に向けたデューデリジェンスの役割
デューデリジェンスは、対象会社の詳細を調査する手続きです。
中堅中小企業の場合、何の問題点もない企業はほとんどありません。
買い手企業は、デューデリジェンスを粗捜しと捉えるのではなく、M&A後にどのように問題点を解決し、対象会社を良くしていくことができるのかという視点を持って取り組むことが重要です。
デューデリジェンス結果の価値評価への反映
主に財務デューデリジェンスの検出事項が取引価格に反映されます。
取引価格への反映において重要なポイントは意向表明書の中でどういった点が減額可能性かを記載しておくことです。
例えば意向表明書に直近の決算書記載の純資産額との異同が価格に反映されると記載したとします。
デューデリジェンスにおいて取引先A社への売掛金20百万円が回収不能と発覚した場合に純資産からの減額要因であるため取引価格から差し引く交渉を行うことができます。
デューデリジェンスとポストM&A戦略
デューデリジェンスでの検出事項はM&A後に治癒する必要があります。
中堅中小企業のM&Aで多い論点が残業代の未払いの問題です。
労働関連の法制度は頻繁に改定が起こりますが、中堅中小企業が法制度の変更に合わせて自社の就業規則などを修正している場合は少ないです。
中堅中小企業では労働時間を正確に計算できていないケースが多いです。
こうした場合にはM&A後に勤怠管理システムを導入するなどが必要です。
設備投資や追加の費用が発生する事項も多いため買い手企業は対象会社の改善に掛かる費用も投資コストとして株式譲渡対価と別に見積もる必要があります。
デューデリジェンスのケーススタディ
成功したM&Aのデューデリジェンス事例
成功するM&Aのデューデリジェンスは売り手に対しての負担をできるだけ軽減することが挙げられます。
上場企業A社が中小製造業B社の株式を譲り受けた事例を紹介します。
B社はオーナー社長が高齢であり、譲渡を決めました。
オーナー社長は従業員等にM&Aを行うことを開示せずにデューデリジェンスを進めていました。
オーナー社長は自社製品などには精通しているものの、経理面などには詳しくなくA社が雇った公認会計士から受け取ったQ&Aリストの質問になかなか答えられずにいました。
A社はM&A仲介会社を通してQ&Aリストの書面でのやり取りではなくマネジメントインタビューの形式で会話をしながら進めることを提案しました。
実際にマネジメントインタビューを進めてみるとA社の本件検討メンバーが公認会計士の質問を適宜補足するなどして進めたため公認会計士が満足する回答を得られることができました。
デューデリジェンスは売り手や対象会社に配慮して進めることが重要です。
デューデリジェンスに失敗したM&A事例
デューデリジェンスの失敗事例としてよく見られる事例は専門家を雇わずに買い手企業が自社でデューデリジェンスをする場合です。
例えば簿外債務などをデューデリジェンスに慣れた公認会計士に依頼しなかったために見落とされるケースは多数あります。
事例から学ぶデューデリジェンスの重要性
デューデリジェンスの初期段階では専門家と売り手や対象会社とはコミュニケーション資産が無い状況でデューデリジェンスを進めることになります。
顔が見えない相手から大量の質問や資料依頼を受け取ることは売り手や対象会社にとって心理的な不安につながります。
適宜インタビューセッションを設けるなど文字だけではないコミュニケーションを取ることが重要です。
デューデリジェンスを支援する専門家とその選び方
必要な専門家の種類と役割
デューデリジェンスを依頼する専門家は公認会計士、弁護士、税理士、社会保険労務士などが挙げられます。
公認会計士には財務デューデリジェンスを依頼します。
弁護士には法務デューデリジェンスを依頼し、最終契約書の作成まで一貫して依頼するとその後の契約交渉が円滑に進められます。
税理士には税務デューデリジェンスを依頼します。
税務デューデリジェンスは財務デューデリジェンスと同じ会計事務所に依頼することが多いです。
社会保険労務士には労務デューデリジェンスを依頼します。
労務デューデリジェンスは弁護士に依頼するケースが大半ですが、弁護士に労務デューデリジェンスを依頼すると費用が高くなる場合が多くそうした場合には社会保険労務士に労務デューデリジェンスを依頼することが多いです。
専門家選びのポイント
専門家を選ぶ際、最初のポイントは、対象会社と同じ業種でのデューデリジェンス経験の有無を確認することです。
デューデリジェンスの相談段階での確認
次に、デューデリジェンスの相談段階で、対象会社の概要を説明した際に、どのような論点が想定されるかを確認します。この時の対話から、専門家が信頼できるか否かを判断できます。
M&A経験の確認
買い手企業に顧問の税理士や弁護士がいる場合もありますが、実際にM&A関連の業務経験があるかを確認することも重要です。経験がない場合には、他の弁護士に依頼を検討することをお勧めします。
専門家との良好な関係の築き方
デューデリジェンスは短い時間の中で実施されるため専門家にも厳しいスケジュールの中で業務を依頼することになります。
専門家に対してM&A検討のスケジュールを事前に伝え、変更があった場合には速やかに伝えるなどコミュニケーションを頻繁に取ることで良好な関係が築けると思います。
また、デューデリジェンスでは専門家間で情報共有・連携が重要な局面があります。
例えば弁護士が算出した未払残業代が財務デューデリジェンスレポートの簿外債務に記載されるなどが挙げられます。
依頼者である買い手企業が専門家どうしの間に入って情報共有を促進することが必要です。
デューデリジェンス・プロセスの中で関係者全員が参加する進捗会議を隔週で設定するなどもお勧めする進め方です。
・M&A時に行う「デューデリジェンス」とは?DDの進め方や注意点をわかりやすく解説
まとめ
多くの時間と労力を必要とし、様々なリスクに対処する必要があるM&Aという大仕事を実施するためには最適な支援パートナーを探すことが重要です。
支援パートナーによってリスクの大小や売却額の多寡も変わってきます。
ご自身が手塩にかけて育ててこられた会社を最適な形で残していくためにも最適な支援パートナーを探すことは非常に重要と言えます。
日本提携支援ではフラットな立場、目線からご支援をさせて頂くことで、売り手側買い手側双方にとって最適な支援パートナー探しをさせて頂きます。
心から納得のいくM&Aを実現して頂くため、何度でも無料でご相談をお受けします。
また、既に他の会社のご支援を受けている場合であってもセカンドオピニオンとしてご相談頂ければと思います。
M&Aについて少しでもご関心をお持ちの場合、すでに検討を開始されて迷われることがあった場合には、お気軽に日本提携支援にご相談ください。
フラットな立場と目線から最適な支援パートナー探しのお手伝いをさせて頂きます。